ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説
公開日:2025年4月2日
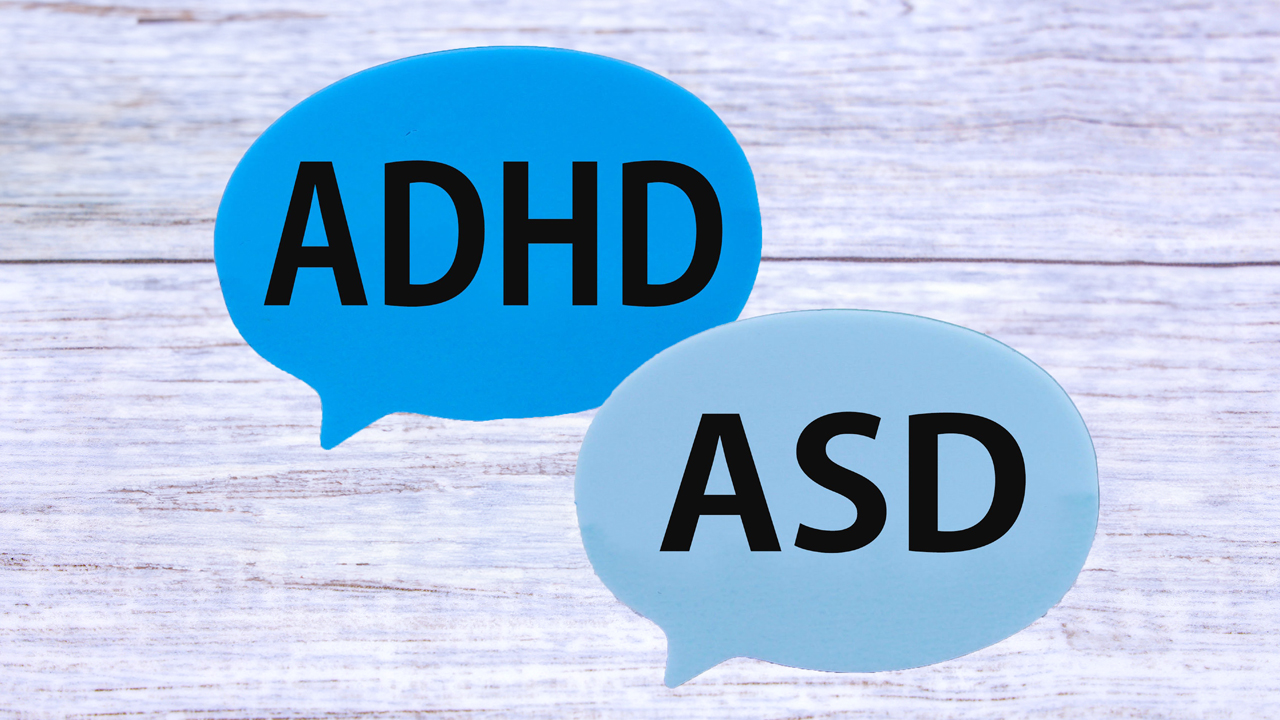
このコラムでは、ADHDとアスペルガー(ASD)の違いを詳しく解説します。さらに、それぞれの特性に応じた困りごとやサポート方法についてもご紹介します。ADHDやアスペルガーへの子育てに悩んでいたり、これらの違いを知りたい方は、是非ご覧ください。
ADHDとアスペルガー(ASD)の基礎知識
発達障害は先天的な脳の特性によるものであり、本人の努力や性格とは関係なく現れます。特にADHDとアスペルガー症候群(現在はASD(自閉スペクトラム症)に含まれる)は、一部の特徴が似ているため混同されやすいですが、それぞれ異なる特性を持っています。
ここでは、ADHDとアスペルガー(ASD)のそれぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
1. ADHDとは?
ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意、多動性、衝動性の三つの特性を持つ発達障害です。
| 不注意の特徴 | 物事に集中しづらい、忘れ物が多い、話を最後まで聞けないといった傾向が見られます。 |
|---|---|
| 多動性の特徴 | じっとしているのが苦手で落ち着きがなく、常に動き回りたがることが挙げられます。 |
| 衝動性の特徴 | 思いついたことをすぐに行動に移してしまう、順番を待つのが難しい、感情のコントロールが苦手といった傾向が見られます。 |
これらの特性は、子どもから大人まで共通して見られるものですが、年齢によって行動の現れ方が変わることもあります。
例えば、子どもの場合は「授業中にじっと座っていられない」といった行動が目立つことが多いですが、大人になると立ち歩きはしないものの、「気が散りやすく仕事が手につかない」「計画的に物事を進められない」といった形で現れることが多くなります。
2. アスペルガー(ASD)とは?
アスペルガー症候群は、現在では「自閉スペクトラム症(ASD)」の一部とされており、対人関係の困難さや強いこだわり、感覚の過敏さなどの特徴を持つ発達障害です。
| コミュニケーション | 会話のキャッチボールが苦手だったり、相手の気持ちを読み取ることが難しかったりする傾向があります。 |
|---|---|
| 強いこだわり | 自分の決めたルールや手順を厳密に守ろうとし、変化に対して強いストレスを感じることも少なくありません。 |
| 感覚の過敏さ | 大きな音や強い光に敏感である場合や、特定の食べ物の食感を極端に嫌うといった特徴が現れることがあります。 |
これらの特性は個人差が大きく、日常生活に大きな影響を及ぼす場合もあれば、軽度で社会生活に適応しやすい人もいます。
3. ADHDとアスペルガー(ASD)の併発の可能性
ADHDとアスペルガー(ASD)は、それぞれ異なる特性を持っているものの、同時に併発することも珍しくありません。
例えば、ADHDの衝動的な行動とアスペルガーのこだわりの強さが同時に現れると、自分のルールに従ってすぐに行動を起こしたり、周囲の状況を考えずに発言してしまったりすることがあります。
また、ADHDの特性として注意が散漫になりやすい一方で、アスペルガー(ASD)の特性として特定の物事に強く集中することがあるため、場面によっては相反するような特性が同時に見られることもあります。
例えば、興味のあることには異常なほど没頭するものの、それ以外のことには全く注意を払えないという状況が生じることがあります。
発達障害チェックリストついてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】」

ADHDとアスペルガー(ASD)の比較|4つの主な違い
ADHDとアスペルガー(ASD)は、それぞれ異なる特性を持っていますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、集中力、対人コミュニケーション、こだわり、興味の偏りという4つの視点から比較していきます。
1. 集中力の違い
ADHDとアスペルガー(ASD)では、集中力の持続の仕方に大きな違いがあります。
ADHDの場合、集中しようとしても周囲の音や動きに気を取られやすく、目の前の作業から気がそれてしまうことがよくあります。また、興味のあることには一時的に強い集中を見せることもありますが、それが長続きせず、すぐに別のものへ意識が移ってしまう傾向があります。
一方で、アスペルガー(ASD)の場合は、興味のあることに対して極端な集中を見せることが多く、一度夢中になると周囲の状況が目に入らなくなることもあります。ただ、特定の分野や作業に対して、長時間にわたって集中を続けられる一方で、興味がないことにはほとんど注意を払わないといった特徴があります。
ADHDの集中力のばらつきとは異なり、アスペルガー(ASD)の場合は「一点集中型」と言えるでしょう。
2. 対人コミュニケーションの違い
ADHDの人は、社交的な一面を持つことが多く、会話が好きで周囲の人と積極的に関わろうとする傾向があります。
しかし、話をしている途中で思いついたことをすぐに口に出してしまったり、相手の話を最後まで聞かずに話し始めてしまったりすることがあり、その結果、無意識のうちに相手を困らせてしまうこともあります。また、場の空気を読むのが苦手なこともあり、思ったことを率直に伝えすぎてしまうことがあります。
対して、アスペルガー(ASD)の人は、対人関係そのものが苦手であることが多く、会話のルールを理解しづらいと感じることがあります。
例えば、相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取ることが難しく、相手の意図とは違う受け取り方をしてしまうことがあります。また、話し方が一方的になりやすく、興味のある話題について延々と話し続けることもあるため、相手との距離感がつかみにくくなりがちです。
3. こだわりの違い
ADHDの人は、整理整頓が苦手なことが多く、片付けても毎回違う場所に物を置いてしまい、結果的にどこに置いたか分からなくなることがよくあります。
計画的に整理するのが難しく、思いついたときに適当に片付けるため、常に探し物をしている状態になることもあります。また、同じやり方にこだわるよりも、そのときの気分や状況に応じてやり方を変える傾向が強いです。
一方、アスペルガー(ASD)の人は、物の配置や片付け方に対して強いこだわりを持つことが多く、決められた順番やルール通りに片付けないと落ち着かないことがあります。
例えば、机の上の物を特定の順番で並べたり、本棚の本を特定のルールに基づいて並べたりすることに強いこだわりを見せることがあります。
このように、ADHDは「こだわりに縛られず自由に行動する」のに対し、アスペルガー(ASD)は「強いこだわりを持って行動する」という違いがあります。
4. 興味の偏りの違い
ADHDの人は、新しいものに興味を持ちやすい一方で、その興味が長続きしにくいという特徴があります。
例えば、ある趣味に夢中になっても、しばらくすると別のことに興味が移ってしまい、前に熱中していたものにはほとんど手をつけなくなることがあります。そのため、次々と新しいことに挑戦するのが好きですが、一つのことを極めるのは難しい傾向があります。
これに対して、アスペルガー(ASD)の人は、特定の分野に対する強い興味を持ち、長期間にわたってその興味が続くことが多いです。
例えば、特定の歴史の時代や科学の分野、特定のアニメやゲームなどに強くこだわり、何年経ってもその興味が変わらないことがあります。また、興味を持った分野について膨大な知識を集めることに熱中する傾向があり、その分野に関しては専門家並みの知識を持っていることもあります。
ADHDが「興味が移り変わりやすい」のに対し、アスペルガー(ASD)は「特定の分野への興味が長く続く」という点が大きな違いです。

ADHDとアスペルガー(ASD)の比較|困りごとの違い
ADHDとアスペルガー(ASD)では、日常生活のさまざまな場面で困りごとが生じますが、その内容は異なります。
学校生活、日常生活、課外活動の三つの場面に分けて、それぞれの特性に基づく困りごとを見ていきましょう。
1. 学校生活での困りごと
学校では、授業を受けたり、先生やクラスメイトと関わったり、集団行動をしたりする機会が多くあります。そのため、ADHDとアスペルガー(ASD)の特性が、さまざまな形で困難を引き起こすことがあります。
ADHDの場合
授業中に集中が続かず、ノートを取るのを忘れたり、先生の話を聞き逃すことや、テスト前にほかのことに気を取られてしまい、なかなか勉強が進まないこともあります。
また、衝動的に発言してしまったり、順番を待つのが苦手だったりするため、クラスの中でトラブルになることも少なくありません。
加えて、提出物の締め切りを守るのが苦手で、宿題やプリントを忘れてしまうことも多く、先生から保護者へ連絡がきて発覚することがよくあります。
アスペルガー(ASD)の場合
授業内容そのものは理解できても、先生の曖昧な指示が分かりにくかったり、グループワークで他の生徒とうまく協力できなかったりすることがあります。
また、相手の表情や気持ちを読み取るのが苦手なため、クラスメイトの何気ない一言を文字通りに受け取り、誤解してしまったり傷ついてしまうこともあります。
加えて、決まったルールや手順に強いこだわりを持っているため、予定変更や予想外の出来事に適応しづらく、集団生活に強いストレスを感じてしまうことがあります。
2. 日常生活での困りごと
家庭やプライベートの場面でも、ADHDとアスペルガー(ASD)ではそれぞれ異なる困りごとが生じます。
ADHDの場合
忘れ物や無くし物が多く、朝の準備に時間がかかることがよくあります。
例えば、カバンや洋服を適当に置いてしまい、次に使うときに見つからないということが頻繁に起こります。
食事やお風呂など、ルーチンワークの途中でほかのことに気を取られ、なかなか終わらないこともあります。
また、計画的に行動するのが苦手で、時間の管理がうまくできず、気がついたら約束の時間に遅れてしまうことも多いです。
アスペルガー(ASD)の場合
生活の中で決まったルールや手順があると安心できる反面、予定が急に変更されると強いストレスを感じやすいです。
食事の際にも、決まった食器や席の配置でないと落ち着かないことがあり、少しでも違うと食事が進まなくなることがあります。
また、感覚過敏がある場合、特定の音や光が苦手で、日常の中でも不快に感じる場面が多くなります。例えば、衣服のタグがチクチクするのが気になって集中できなかったり、人混みの騒音がストレスになったりすることがあります。
3. 課外活動での困りごと
学校以外の習い事や部活動、遊びの場でも、それぞれの特性によって困難を感じることがあります。
ADHDの場合
スポーツや体を動かす遊びが好きなことが多いですが、ルールを守るのが苦手なことがあります。例えば、サッカーの試合中に急に別のことに気を取られてしまったり、衝動的にボールを手で触ってしまったりすることがあります。
また、チームプレーよりも自分の思いつきで動くことが多いため、協力しながら進める活動では注意されることが多くなります。さらに、道具をなくしたり、持ち物を忘れたりすることもよくあります。
アスペルガー(ASD)の場合
団体競技などで周囲と協力することが求められる場面では、コミュニケーションがうまく取れずに孤立してしまうことがあります。
決まった動作を繰り返す競技や個人競技では力を発揮しやすいですが、試合の流れに応じて臨機応変に対応することが苦手なため、チームプレーには難しさを感じることがあります。
また、特定の趣味や活動に強いこだわりを持っているため、自分の興味のあること以外にはあまり参加したがらないこともあります。
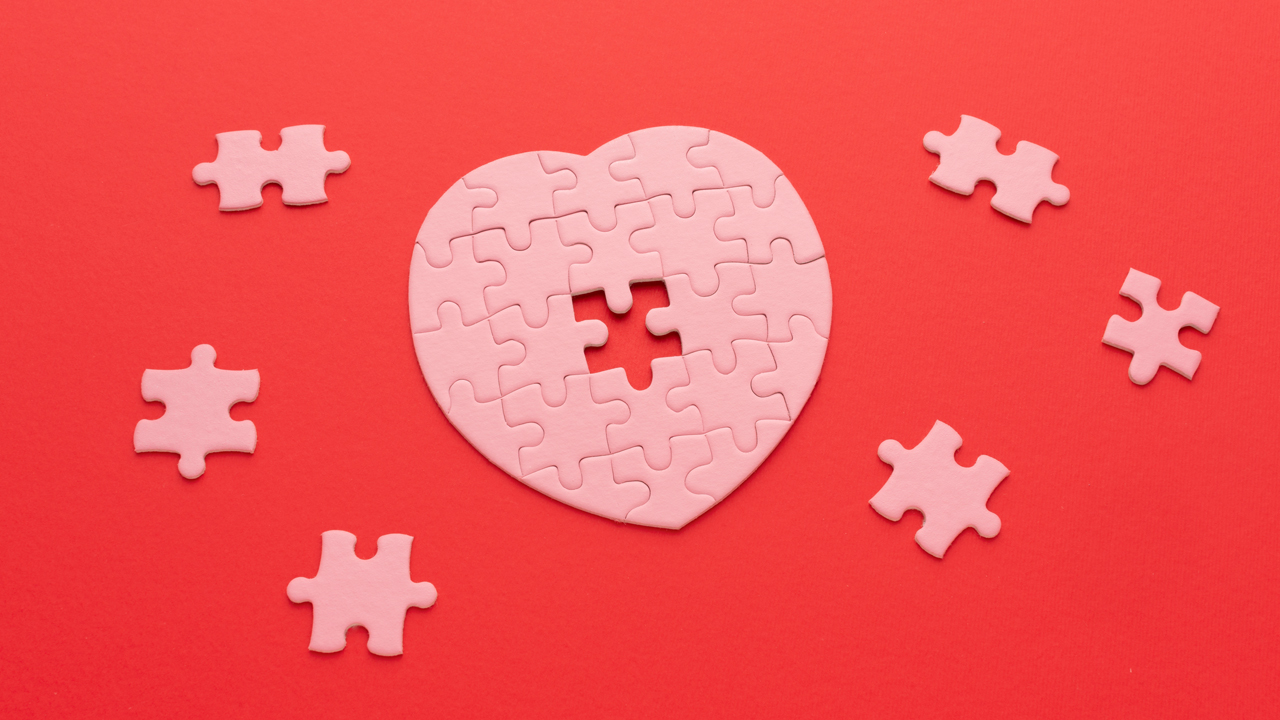
ADHD・アスペルガー(ASD)を持つ子どもへのサポート方法
ADHDやアスペルガー(ASD)の特性を持つ子どもは、それぞれ異なる困難を抱えています。しかし、適切なサポートを行うことで、日常生活や学校生活がよりスムーズに進むようになります。
ここでは、ADHDとアスペルガー(ASD)の子どもに対する具体的な支援方法について紹介します。
1. ADHDの子どもへのサポート方法
ADHDの子どもは、集中力を維持することが難しく、忘れ物が多かったり、衝動的に行動してしまったりすることがあります。そのため、環境を整えたり、行動をサポートしたりすることが大切です。
整理整頓が苦手な子の場合
整理整頓が苦手な子の場合、片付けやすい環境を作ることが効果的です。
例えば、ランドセルや勉強道具の定位置を決め、色分けやラベルを使って分かりやすくすることで、物の管理がしやすくなります。
また、学校の宿題や持ち物のチェックリストを作成し、視覚的に確認できるようにするのも有効でしょう。
時間管理が苦手な子の場合
時間管理が苦手な子の場合、アラームやタイマーを活用し、「今から〇〇をする時間」と区切ることで、次の行動に移りやすくなります。
また、勉強や宿題をするときは、長時間続けるのではなく、短い時間ごとに休憩を挟む「ポモドーロ・テクニック」のような方法を取り入れると、集中しやすくなることがあります。
衝動的な行動をしてしまう子の場合
衝動的な行動を抑えるためには、ルールをシンプルにし、具体的な指示を与えることが重要です。「静かにしなさい」ではなく、「先生が話している間は手を膝に置いておこう」といった形で、具体的な行動を伝えると理解しやすくなります。
また、成功体験を増やすことも大切です。「最後まで宿題を終えられたね」「時間通りに準備ができたね」と、小さな達成を積み重ねることで、子ども自身の自信につながります。
叱るよりも、できたことを褒めることを意識すると、子どもが前向きに行動しやすくなります。
2. アスペルガー(ASD)の子どもへのサポート方法
アスペルガー(ASD)の子どもは、コミュニケーションが苦手であったり、こだわりが強かったり、感覚過敏を持っていたりすることが多いです。そのため、無理に一般的なやり方に合わせるのではなく、子どもの特性に合った環境を整えることが大切です。
コミュニケーションが苦手な子の場合
コミュニケーションが苦手な子には、曖昧な表現を避け、具体的で分かりやすい言葉を使うことが重要です。例えば、「しっかりやりなさい」ではなく、「宿題を終えたら先生に提出しよう」といったように、何をどうすればよいのかを明確に伝えると理解しやすくなります。
急な予定変更に対応するのが難しい子の場合
急な予定変更に対応するのが難しい子の場合、スケジュールを事前に伝え、できるだけ変更を少なくすることが望ましいです。
予定が変わる場合には、理由を説明し、少しずつ変化に慣れるようにサポートすると、安心しやすくなります。
こだわりが強い子の場合
こだわりが強い子の場合には、そのこだわりを否定せず、適切に活用することが有効です。
例えば、特定の分野に強い興味を持っている場合、その興味を学習や生活の中に取り入れることで、楽しく学ぶことができます。
また、こだわりによるストレスが大きくならないように、ルールを少しずつ柔軟にする練習を行うのも良い方法です。
感覚過敏がある子の場合
感覚過敏がある場合には、子どもが苦手な刺激をできるだけ減らす環境を整えることが大切です。
例えば、大きな音が苦手ならノイズキャンセリングイヤホンを使用する、服のタグが気になるなら取り除くなど、子どもが安心できる環境を作ることが重要です。

まとめ
ADHDとアスペルガー(ASD)は、それぞれ異なる特性を持っており、学校生活や日常生活、課外活動などさまざまな場面で違った困りごとが生じます。しかし、その個性を理解し、適切なサポートを行うことで、子どもの持つ才能やポテンシャルを最大限に伸ばすことができます。
大切なのは、子どもの気持ちや特性を尊重し、一人ひとりに合った支援を続けていくことです。周囲の理解が深まり、サポートが適切に行われることで、子どもたちは自信を持ち、自分らしく成長していくことができるでしょう。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!























