高校受験の勉強って何からすればいい?|中学生の為の受験勉強ガイド
公開日:2025年3月31日
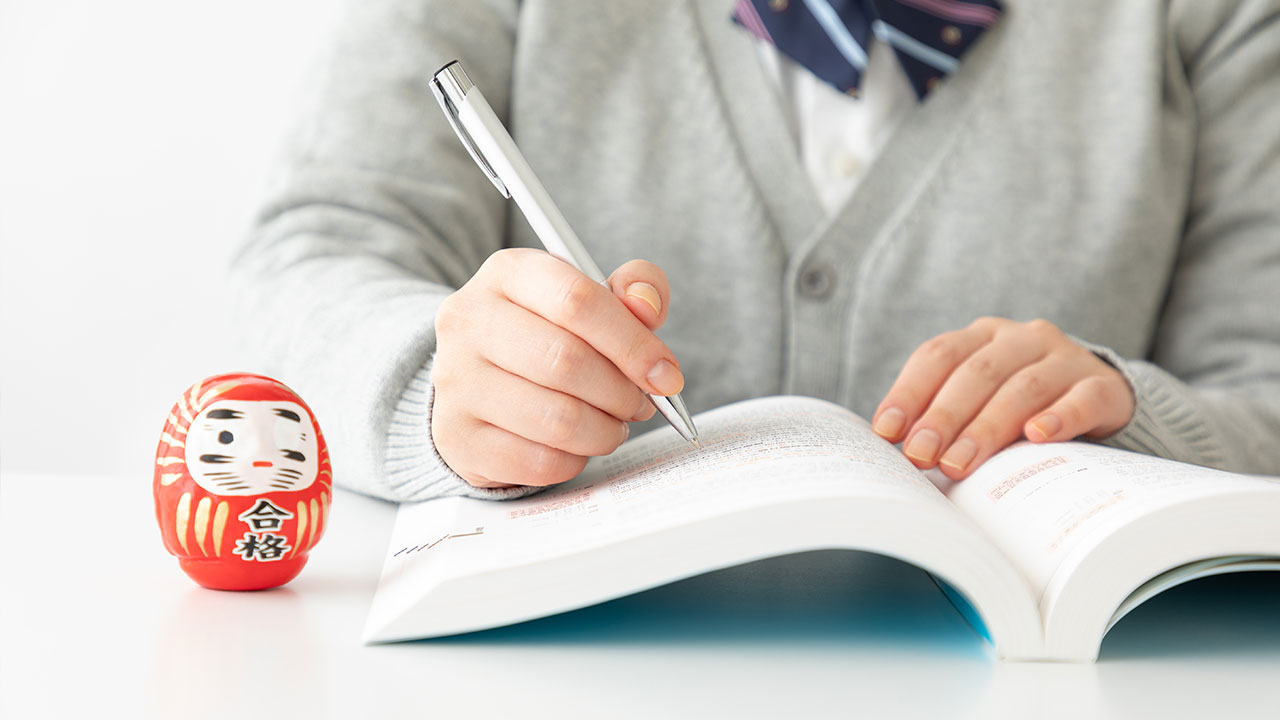
「中学生の高校受験勉強って何を勉強すればいい?」そんな疑問を持つ中学生に、高校受験勉強のやり方について詳しく解説します。
また、受験勉強を始める前の準備、受験勉強でやること、効果的な勉強法、やってはいけない勉強法についてもご紹介します。
受験勉強は何から始める?|最初にやるべき4つの準備
STEP1|自分の学力を確認する
受験勉強を開始する前に、まず自分の現在の学力を正確に把握することが大切です。自分の学力を把握するための方法としては、「偏差値」と「内申点」の2つがあります。
自分の偏差値は、模擬試験や地域で実施される実力テストを通じて確認できます。これにより、全体の中で自分がどの位置にいるのかが分かり、受験勉強の目標偏差値を設定することができます。
また、内申点は過去の通知表の成績から概算できます。内申点の計算方法や評価基準は地域や学校によって異なるため、教育委員会や学校の先生に確認しておきましょう。
偏差値の意味や求め方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「偏差値って何だろう?|偏差値の意味や求め方(計算方法)を解説」
内申点の計算についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点の計算方法|自分の点数をシミュレーションしてみよう!」
STEP2|志望校を決める
受験勉強を進める上で、志望校を決めておくことは非常に重要です。自分の学力を確認した後、次に行うべきは志望校を決定して目標を定めることです。
志望校は必ずしも1校に絞る必要はなく、第1希望から第5希望までをあらかじめ決めておくと良いでしょう。最終的に受験する高校を決めるのは、中学3年生の夏頃になります。
自分の学力に合った学校を選ぶことが大切ですが、公立・私立を含めると候補となる学校が多くなるかもしれません。そのため、校風や立地、部活動、制服のデザインなど、さまざまな要素を考慮して絞り込んでいきましょう。
学校の先生や先輩、家族や友人と情報や意見を交換しながら、最も自分に合った学校を選びましょう。
志望校の決め方・高校選びのポイントについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「志望校の決め方ガイド|高校選びのポイント解説【中学生向け】」
STEP3|学習計画を立てる
志望校が決まった後は、受験日を目標にした学習計画を立てる段階に進みます。
受験日はあらかじめ決まっているので、その日から逆算して勉強計画を作成します。推薦入試を考えている場合は、受験日程が早まるため、少し早めに準備を始める必要があります。
学習計画は、数学・国語・英語・理科・社会の5科目について、具体的に「何をいつまでにやるか」という内容で計画を立てましょう。漠然とした計画では効果が薄いため、細かい内容まで決めておくことが重要です。
また、過去のテスト結果をもとに自分の苦手科目や苦手分野を洗い出し、課題感を持って取り組むことも必要です。
学習計画を立てる過程で自己分析を行うこともできるため、受験勉強のスタート時点でしっかりと取り組みましょう。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」
STEP4|学習ツールを選ぶ
受験勉強を効率的に進めるためには、学習ツールの選定も非常に重要です。
受験勉強においては、どの方法で勉強を進めるかを事前に決めておくことが大切です。数学・国語・英語・理科・社会の5科目について、それぞれどのように学習を進めるかを考えましょう。
具体的には、「どの問題集やテキストを使用するか」や「塾・家庭教師・通信添削などの学習支援を利用するか」を選びます。
重要なのは、学習方法を一貫して続けることです。色々な方法を試したり、頻繁に学習方法を変えてしまうと、学習効率は著しく低下します。ひとつの方法を繰り返し実践することで、着実に学力が向上していきます。
自分の学力やニーズに最も適した学習ツールを選び、効果的な勉強を行いましょう。
塾と家庭教師についてもっと知りたい方はこちら
⇒「塾と家庭教師どっちがいいの?|どちらが子供に合うか徹底検証!」

受験勉強って何をやればいい?|5つの受験対策方法
受験勉強を進めるうえで、どの部分に力を入れるべきかを知っておくことは非常に重要です。
受験には、学力試験に加えて内申点や面接、小論文など、さまざまな要素が関わっています。それぞれの対策方法をしっかりと把握し、計画的に取り組んでいきましょう。
このセクションでは、受験に向けた5つの対策方法をご紹介します。
1. 内申点の対策
受験では、学力検査(入試テスト)と並んで、内申書(内申点)の評価も重要な役割を果たします。
内申点は、入試の合否を左右する決定的な要素となり得るため、しっかりと対策をしておく必要があります。内申点は主に通知表の成績に基づいて算出され、その成績は定期テストの点数によって大きく左右されます。
特に中学3年生の成績は直近の学力を反映しており、最も重視されます。中学3年生の定期テストを頑張ることがそのまま受験勉強に直結するとも言えるのです。
高校受験の内申点についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験の内申点とは?|内申書(調査書)・内申点の基礎知識ガイド」
2. 学力試験の対策
学力試験はほとんどの高校受験で実施され、公立高校の受験科目は英語、数学、国語、理科、社会の5科目がほとんどです。私立高校の場合は、英・数・国の3科目が一般的です。
出題範囲は中学1年生から3年生までの全範囲にわたります。これは、教科書15冊分の内容をカバーするため、1~2ヶ月では到底終わらない量です。
ですから、なるべく早い段階から学習を始めることが必要で、理想的には中学2年生の冬から対策を始め、遅くとも中学3年生の夏には開始することが望ましいです。
苦手科目を中心に学習し、得意科目も再確認することで、死角を減らすことが合格へのカギになります。繰り返し演習を行い、計画的に進めましょう。
高校受験の勉強法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験の勉強法とは?|科目別・時期別に詳しく解説!」
3. 過去問の対策
受験勉強において、過去問を解くことは非常に重要です。過去問は自分の学力を実感し、問題慣れをするだけでなく、時間内に解く力を養うためにも効果的です。
志望校の過去問を解くのはもちろんですが、少しレベルを下げた学校の過去問にも取り組むことをおすすめします。特に、受験勉強を始めたばかりの頃は、少しレベルを下げた問題を解くことで自信をつけられます。
過去問を解く頻度としては、1〜2ヶ月に一度が理想です。毎回点数の差を確認し、自分の成長を感じることがモチベーションを維持するポイントです。
4. 面接・小論文・作文の対策
面接や小論文・作文は、特に推薦入試で必要な試験科目です。これらは学校の授業で詳しく学ぶことが少ないため、独自の対策が求められます。
面接では、よく聞かれる質問パターンに備えておき、自分の志望理由や長所、短所、時事問題への意見などについて、あらかじめ練習しておくことが重要です。
また、時事問題や社会問題は面接・小論文のテーマになりやすいため、日頃からニュースをチェックし、考えをまとめておくことが必要です。
面接や小論文の練習は第三者(家族や先生)に添削してもらうことをおすすめします。
高校受験でよく聞かれる質問10選
⇒ 「高校の面接でよく聞かれること|10種類の質問と回答例をご紹介!」
高校入試の小論文についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校入試の小論文の丸わかり完全攻略ガイド!|模範解答例・解説付き」
作文の書き方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校入試の作文の書き方と注意点|カンタン早わかりガイド!」
5. 模擬試験の活用
受験に向けた模擬試験は、自分の実力を測る最も重要なデータとなります。
模擬試験の結果を通じて、自分の偏差値や合格可能性を確認することができ、さらに苦手科目や分野を洗い出す手助けになります。
模擬試験の結果を分析し、自分の弱点を明確にし、その部分を強化することが合格への近道となります。また、模擬試験では、時間制限を守って問題を解くことを練習する場ともなります。
模擬試験を受け、試験本番に向けた練習を積むことで、実際の試験でも落ち着いて臨むことができます。

効果的な5つの受験勉強法
受験勉強を効果的に進めるためには、各科目において必要な知識をしっかりと定着させ、応用力を身につけることが重要です。
以下では、受験に役立つ5つの効果的な対策方法を紹介します。これらを計画的に実践することで、合格に向けた実力を着実に高めていきましょう。
1. 単語・文法・公式・語彙の暗記
受験勉強では、暗記が欠かせません。特に、単語や文法、公式、語彙は、どの科目でも基本的な知識として身につけておく必要があります。
これらは一度にすべて覚えるのが難しいため、毎日の学習に少しずつ暗記を組み込むことが大切です。コツコツ積み重ねていくことが確実に点数に結びつくので、毎日のルーチンとして暗記作業を習慣にしましょう。
暗記は根気が必要ですが、自分に合った暗記法を見つけることが重要です。効率的な暗記法については、下記で詳しくご紹介していますので、ご興味のある方はご覧下さい。
効果的な暗記方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効率的な暗記の方法とは?|苦手な暗記を克服するオススメ8つの方法」
2. 基礎力の定着
受験勉強において、基本問題を確実に解く力を身につけることは非常に重要です。
基本問題を解けるかどうかは、合否に大きな影響を与えており、特に、周りの受験生が簡単に解ける問題を間違えてしまうと、大きな差がついてしまいます。
基本問題を確実、正確、スピーディーに解けるようにするために、繰り返し演習を行いましょう。
この中でもスピードが特に重要です。基本問題を早く解けるようになれば、その分、難易度の高い問題や応用問題に時間を割くことができ、受験を有利に進めることができます。
基本問題をしっかりと理解し、得点源にすることが合格への鍵となります。
ケアレスミスについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ケアレスミスが多い小中高生|効果的な7つの対策法」
3. 関連分野をまとめる
それぞれの科目には、分野間の関連性があります。これを理解しておくことが、応用問題に強くなるためのポイントです。
例えば、理科や社会では、分野ごとの関連性を整理してノートにまとめておくと、効率的に学習できます。
また、英語や数学、国語などでも分野間の繋がりを意識した学習が効果的です。
例えば、数学では「方程式」「連立方程式」「二次方程式」を体系的にまとめ、英語では「現在形」「過去形」「現在完了形」を動詞ごとに整理するなど、学習の幅を広げながら理解を深めていきましょう。
こうした整理や体系的な理解を進めることで、応用問題に強くなり、解答スピードも向上します。
ノートのまとめ方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ポイントを押さえたノートまとめ方のコツ|小中学生向け簡単ノート術!」
4. 長文読解や文章問題の演習
高校受験では、長文読解や文章問題の配点が高いことがほとんどです。
特に、英語や国語の長文読解では、スピードと正確さが求められ、これらの問題を解けるか解けないかが合否に大きく影響します。
読解のスピードを上げるためには、おおよそ7〜8割程度を速読で理解できるように訓練することが重要です。
これを実現するためには、できるだけ多くの文章を読み、時間を計りながら速読を意識して練習することが大切です。
また、「問題文を先に読んでから文章を読む」という方法も有効です。これにより、文章の方向性を掴みやすくなり、読解がスムーズになります。
数学などの文章問題も同様に、問題パターンを把握して、多くの問題を解くことで理解を深めることができます。特に、問題文の主旨を素早く理解する力が重要で、これには国語力も大きく影響します。
英語の長文読解についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「英語の長文読解のコツ|問題の解き方から勉強法まで徹底解説!」
5. 面接・小論文・作文の演習と添削
面接や小論文・作文の練習は、自分一人では自己評価が難しい部分があるため、第三者からの添削を受けることが不可欠です。
面接の回答や小論文・作文の内容が良いかどうかは、第三者の目で客観的に評価してもらうことで、より良い内容に改善できます。
特に推薦入試では、面接や小論文・作文の比重が50%を占めることが一般的です。
推薦入試を考えている場合は、なるべく早い段階から面接や小論文・作文の対策を始めることをお勧めします。

やってはいけない6つのNG勉強法
受験勉強を進めるうえで、効果的な勉強法を取り入れることが大切ですが、逆に避けるべき勉強法もあります。これらのNG勉強法を知り、意識して避けることで、より効率的に学習を進め、実力を確実に向上させることができます。
以下では、やってはいけない勉強法について解説します。
1. 詰め込み型の勉強
詰め込み型の勉強は、受験前に「短期間で大量の情報を詰め込む方法」ですが、これは学力を定着させる方法としては効果的ではありません。
受験直前に「一夜漬け」をしても、記憶が定着する前に試験が終わってしまうため、試験の結果に結びつきにくいのです。
学習内容が膨大である受験勉強においては、計画的に進め、定期的に復習を繰り返すことが重要です。
詰め込み型の勉強によって短期的に覚えた内容は、長期にわたって覚えておくことが難しく、結局は理解が不十分な状態で試験に臨むことになります。毎日の少しずつの積み重ねと、繰り返しの復習を重視しましょう。
テスト勉強についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「テスト勉強の悩み解決! 3時間睡眠とオール、どっちがベスト?」
2. 一つの科目に偏る
受験勉強では、一つの科目に偏って学習することは避けるべきです。
例えば、得意科目にだけ集中し、苦手科目を後回しにしてしまうことは、全体的な成績を伸ばす上で非常に危険です。特に、入試では全科目が均等に評価されるため、全科目をバランスよく学習することが大切です。
一科目ばかりに偏ると、他の科目で点数が取れず、総合的な得点が低くなる可能性があります。苦手を克服するための時間も確保しつつ、全体的な実力をバランス良く高めるようにしましょう。
3. 間違えた問題をそのままにする
間違えた問題をそのままにして進めることは、最も避けるべき勉強法の一つです。
間違えた問題に対して、なぜ間違えたのかをしっかりと理解しないまま次に進んでしまうと、同じミスを繰り返し、結局は点数に結びつきません。
間違えた問題は、解き直しをしてしっかり理解し、解法を覚えることが大切です。また、間違えた問題のタイプや原因を分析して、自分の弱点を把握し、そこを克服するための学習をしましょう。
間違えた問題が解けるようになることこそが、成績向上への近道です!
4. 沢山の参考書・問題集を使う
参考書や問題集をたくさん使うこともNGです。
確かに、色々な教材を使いたくなる気持ちは分かりますが、教材を増やすことで学習が散漫になり、効率が悪くなります。
多くの教材に手を出してしまうよりも、一つの教材に集中して深く学習する方が断然効果的です。
自分に合った参考書や問題集を選び、その教材を繰り返し何度も使うことが学習の効率を高めます。後から何度でも解き直せるように、解答は直接書き込まず、ノートに書くようにしましょう。
5. 無理な時間割を組む
受験勉強でよくある失敗の一つが、無理な時間割を組んでしまうことです。
「一日中勉強しなければならない」と思い込み、過度に詰め込んだ時間割を組むことがありますが、これは計画倒れに繋がり、結局勉強が続かない原因になります。
勉強計画は、自分が継続できる範囲で設定することが大切です。最初から長時間勉強することを目標にするのではなく、短時間でも集中して勉強を続けることが、長期的に見て効果的です。
自分のペースで、休憩を取りながら無理なく学習を進めていきましょう。
6. 基礎をおろそかにする
受験勉強において、基礎を疎かにすることは致命的な失点に繋がります。
特に、ケアレスミスが多い場合や、難しい問題ばかりを解こうとして基礎問題を後回しにすることは、勉強の効果を台無しにしてしまいます。
難しい問題に挑戦することは大切ですが、まずは、基礎を徹底的に固めることが重要です。基礎がしっかりと定着していないと、応用問題に取り組んでも正しい解法を導くことができません。

まとめ
受験勉強を成功させるためには、計画的で効率的な学習が重要です。
やってはいけないNG勉強法を避け、基礎を固めながら、定期的な復習や演習を繰り返すことで、確実に実力を伸ばしていきましょう。
無理のないペースで継続することが、最終的な成功へと繋がります。勉強法を見直し、自分に合った方法で学習を進めることが、受験の合格を引き寄せるカギです。
家庭教師のマスターでは、高校受験生への受験サポートも行っています。ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【高校受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
この記事に関連するコラム
-
高校受験はいつから間に合う?|始める時期と準備について
-
高校受験はいつ?|【令和7年度】関東・関西の試験日程、願書締切日
-
【中学生必見】高校の種類とその特徴を詳しく解説
-
高校推薦(スポーツ推薦)で進学する方法とは?
-
内申点は高校受験に関係ない?|合否への影響度について解説!
-
高校受験の面接で落ちる人ってどんな人?|失敗例と対策方法について
-
内申点はどこから高い?どこから低い?|内申点の目安を解説!
-
内申点オール3の偏差値は?|オール3の学力位置と目指せる高校
-
高校受験で必要な勉強時間はどれくらい?|学年・時期・偏差値ごとに解説
-
【高校受験】効率の良い受験対策・受験勉強の方法をご紹介します!
-
高校の推薦入試対策ガイド|ここだけは知っておきたいポイント
-
副教科の勉強法について|テストで高得点を取るための対策
























