高校受験の内申点とは?|内申書(調査書)・内申点の基礎知識ガイド
公開日:2025年3月25日
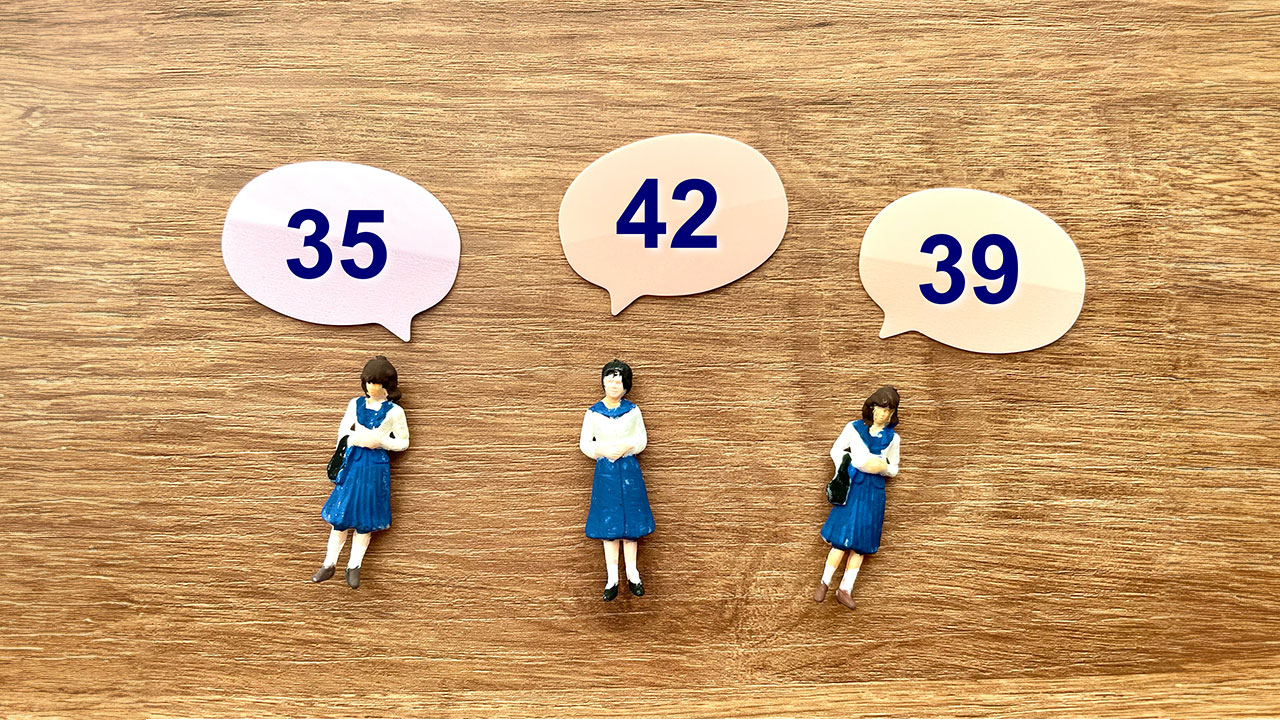
「内申点って何だろう?」そんな疑問を持つ中学生や保護者の方に、「内申点」について基礎からわかりやすく解説します。内申点の仕組み、算出方法、合否に与える影響、内申点を上げるための対策などをまとめて解説します!
内申点の基礎知識
高校受験を控える中学生にとって「内申点」はとても重要になります。しかし、内申点が具体的に何を指しているのか、どのように高校受験に関わってくるのかを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
ここでは、内申点の基本的な知識について詳しく解説していきます。
1. 内申点とは何?
内申点とは、調査書に書かれる内容の一部であり、中学校での成績や生活態度、活動状況を総合的に評価し、最終的に受験用にまとめられた数値のことです。
具体的には、通知表の成績(各教科の評定)を基に計算されることが一般的ですが、それ以外の学校生活全体の取り組みも内申点に反映されます。
内申点の役割
内申点は、高校入試の際に「調査書」として高校に提出されます。そして、入試の合否判定では「学力検査(当日のテストの点数)」と「内申点」を総合的に評価する方式が一般的です。
学校や地域によっては「内申点の比率が高い」「学力検査重視」など、合否判定における内申点のウエイトが異なるので、志望校の基準を事前に確認することが重要です。
調査書(内申書)についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「調査書(内申書)について徹底解説!|高校受験に向けて正しく理解しましょう!」
内申点の重要度
内申点の重要度は、受験する高校や地域によって異なりますが、特に公立高校を受験する場合や、推薦入試で受験する場合は、内申点が大きなウエイトを占めるケースが多く、内申点が高ければ高いほど有利になる場合が多いです。
内申点のメリットは、学力試験を受ける前から有利な状況を作れることにあります。
学力試験は一度きりの勝負であり、予想以上にうまくいくこともあれば、緊張などで実力を発揮できないこともあるなど、不安定な要素を含んでいます。そのため、事前に内申点をしっかり確保しておくことは、大きな安心材料となるでしょう。
一方で、デメリットとしては「一度ついた成績は後から変更できない」という点が挙げられます。地域によっては中学1年生の成績から内申点に反映される場合も多く、過去の成績が振るわないと、いざ受験の際に不利になってしまうことがあります。
内申点に含まれる内容とは?
内申点に含まれる内容は、主に次の3つです。
1. 評定(各教科の評定点)
主要5教科(国・数・英・理・社)と実技4教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)の9教科の通知表の評定(1〜5段階)がもとになります。
3年生の成績が重視されますが、学校や都道府県によっては1・2年生の成績も加味される場合も多いです。
2. 学校での活動状況
委員会活動、生徒会、ボランティア活動、部活動などへの取り組み姿勢や実績も評価対象になることがあります。
3. 生活態度・出席状況
日々の授業態度や提出物の状況、欠席日数や遅刻・早退の有無など、日常の生活面も評価対象です。
地域によって異なる内申点の計算方法
内申点の計算方法は地域によって大きく異なります。
例えば、中学1〜3年生までの成績を全て対象にする地域もあれば、中学3年生の成績のみを対象にする地域もあります。
また、中学3年生の成績のみを二倍で計算する地域もあれば、技能4科目の成績を二倍で計算する地域もあります。
内申点の算出方法については、各都道府県の教育委員会で公表されています。
内申点の計算についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点の計算方法|自分の点数をシミュレーションしてみよう!」
2. 内申点と通知表は関係ある?
「内申点」と「通知表の成績(評定)」は密接に関係しています。実は、内申点は基本的に通知表の成績をもとに計算されているのです。
内申点は通知表を元に付けられている!
通知表に記載される各教科の「評定(1〜5段階)」が、内申点のもととなります。この評定を総合的に評価したものが内申点としてまとめられ、調査書に記載されて志望校に提出されます。
通知表は通常、学期ごとに評定がつけられますが、内申点は1年間を通してつけられる評価です。そのため、1学期から3学期までの通知表の評定の平均値が内申点の目安となります(あるいは、学年末の評定に近い点数とも言えます)。
いずれにせよ、内申点は通知表の成績と密接に結びついており、「通知表で3なのに内申点で5になる」といったことは基本的にありません。
なお、調査書に記載される内申点は、本人や保護者には正式には公開されません。ただし、通知表の成績をもとに、自分の内申点をある程度推測することは十分可能です。(内申点の具体的な算出方法については後述します)
通知表の評価方法とは?
では、内申点の基になっている「通知表の評定」はどのように決まるのでしょうか?
この点については、2020年度から導入されている「観点別評価」という評価方法が基準となっています。
観点別評価とは、「知識・技能」「 思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から総合的に判断し、評定点を決める方法です。
| 知識・技能 | ・定期テストや小テストの成績 |
|---|---|
| 思考・判断・表現 | ・記述問題や表やグラフの読み取る問題の成績や内容 ・ノートやレポートなどの内容 ・作文や小論文の成績や内容 |
| 主体的に学習に 取り組む態度 | ・ノート、レポート、ワークなどの提出状況や内容 ・授業態度(発表、発言、取り組み方) ・学習に取り組む姿勢 |
通知表の評定は、上記3つの観点をバランスよく評価して決められますが、実際にはテストの点数(知識・技能)が最も大きな影響を与えます。
とはいえ、たとえテストで満点を取ったとしても、提出物をまったく出さなかったり、授業態度が非常に悪かったりすれば、最高評価の「5」はつかない可能性が高くなります。一方で、提出物や授業態度が完璧でも、テストの点数が低ければ「5」を取るのは難しくなります。
つまり、通知表で良い成績を取るためには、テストの点数だけでなく、提出物や授業態度といった3つの観点がバランスよくそろっていることが求められます。
参照:文部科学省「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」
3. 内申点が高校受験に与える影響
内申点は、受験の種類や高校の方針によって重要度が変わります。ここでは、一般入試と推薦入試の場合に分けて見ていきましょう。
一般入試の場合(公立・私立)
一般入試では、ほとんどの高校が「学力検査(当日の試験)」+「内申点」の合計で合否を判断します。
[公立高校]
公立高校の一般入試では、総合得点のうち20%〜40%程度が内申点として加算されます。この割合は都道府県や志望する高校によって異なるため、必ず事前に確認しておくことが重要です。
一般入試では、学力試験が必ず行われますが、実際には試験当日より前に、内申点によって既にある程度の差がついている状態です。
そのため、内申点が高いほど有利に受験を進めることができ、試験本番で多少ミスをしても合格ラインを維持できる可能性が高まります。
逆に、内申点が低い場合は、当日の試験で高得点を取って内申点のハンデをカバーしなければならないため、合格はやや厳しくなると言えます。
[私立高校]
私立高校の一般入試(オープン入試)では、基本的に学力試験の結果でほぼ合否が決まると考えておいて良いでしょう。つまり、内申点はほとんど重視されず、試験当日の一発勝負が一般的です。
ただし、受験者の中でボーダーライン上に複数人が並んだ場合などには、内申点が参考資料として活用されることがあります。したがって、内申点が全く無関係というわけではなく、場合によっては合否を左右する材料となる可能性もある点には注意が必要です。
推薦入試の場合(公立・私立)
推薦入試では、内申点がより大きな影響を持ちます。
学校によっては「内申基準」を設けており、「内申点が〇〇点以上で推薦が可能」といった条件が設定されることもあります。
[公立高校]
公立高校の推薦入試では、内申点と、面接・小論文・作文などの選考試験を合わせた総合得点で合否が決まります。学校によっては、これに加えて適性検査(筆記試験)を課す場合もあります。
推薦入試は、一般入試とは異なり学力試験(筆記試験)が実施されないケースが多いため、内申点が総合得点の50%前後を占めることが一般的です。
面接・小論文・作文は、ある程度の準備をしていれば大きな点差がつきにくいとされており、実質的には内申点が合否を左右する大きな要素になっています。
[私立高校]
私立高校の推薦入試には、主に単願推薦と併願推薦という2つの制度があります。
単願推薦は、合格した場合はその私立高校に必ず進学することが条件で、他の高校は受験できません。
併願推薦は、公立高校を第一志望とする生徒が利用する制度で、公立高校が不合格になった場合は、その私立高校に進学することが前提となります。
どちらの推薦制度でも、合否は内申点と面接・小論文・作文などの選考試験の合計点で決まります。私立高校でも内申点の比重は50%程度が一般的で、公立高校と同様に、「内申点が合否を大きく左右する」と言われています。
このため、私立の推薦入試でも内申点の高さは非常に重要で、推薦をもらうためには、中学3年間の積み重ねが大切になります。
高校の推薦入試についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校の推薦入試について|推薦入試の仕組みをわかりやすく解説!」

内申点の算出方法
ここでは、内申点のおおよその算出方法について詳しく解説します。
実際の調査書(内申点)は非公開のため、正確な点数は分かりませんが、通知表の成績をもとにすれば、おおよその内申点を推測することが可能です。以下の手順に沿って確認してみましょう。
STEP 1|対象の学年を調べる
まずは、自分が住んでいる地域の入試制度を調べましょう。地域によって、内申点の対象となる学年が異なります。
・中学1〜3年生すべての成績が内申点に含まれる地域
→ 中学1年生から3年生までの通知表を準備しましょう。
・中学3年生の成績のみが内申点に含まれる地域
→ 中学3年生の通知表のみでOKです。
なお、3年生の通知表が年度末まで出ていない場合は、直近の学期末の成績を使って計算します。
STEP 2|自分の通知表を調べる
次に、各科目の評定(5段階評価の数値)の平均値を学年ごとに計算してみてください。小数点は四捨五入しましょう。学期ごとの成績に開きがあるようでしたら、学年末の評定を参考にしてみてください。学年末の評定は、1年間を通した評価をつけるようになっていますので、こちらの数値の方が適している場合もあります。
STEP 3|自分の素点を知る
STEP 2で算出した各学年各科目ごとの数値が、最終的な内申点のもとになる「素点」となります。
例えば、中学1年生の評定がオール3であった場合、3×9科目=27点が素点の合計値となります。この素点を対象となる学年ごとに9科目すべてを算出しましょう。
STEP 4|地域の計算式に当てはめる
次に、地域ごとの計算ルールに従って、素点を内申点に換算します。
計算方法は、各自治体の教育委員会や学校の資料で確認してください。地域ごとに計算式は異なるので、誤った方法で計算しないよう注意が必要です。
よくある計算方法の例としては、
- 技能4科目の評定を2倍で計算する
- 中学3年生の評定を2倍で計算する
などがあります。
これらを踏まえて最終的に算出された数値が、実際の内申点にかなり近いものとなります。この内申点が調査書に記載され、志望校に提出されることになります。
実際の高校受験では、内申点・学力試験・面接などの総合点で合否が判断されますが、この配点の割合は高校ごとに異なります。
内申点が重視される学校もあれば、学力試験を重視する学校もあります。
各高校の配点比率は、毎年各都道府県や高校の要項で公表されるので、志望校を選ぶ際には必ず確認しておきましょう。
内申点の換算方法について
⇒ 【内申点計算機】はこちらから

内申点を上げる方法
ここでは、内申点を向上させる具体的な方法について解説します。
結論から言えば、通知表の評定を上げることが、内申点アップに直結します。そのためには、まず「通知表の評定がどのように決まるのか」を理解することが重要です。
1. 通知表の成績を上げることが内申点アップのカギ
内申点を上げるには、通知表の評定を上げることが不可欠です。
通知表の評定は、
「知識・技能」
「思考・判断・表現」
「主体的に学習に取り組む態度」
の3つの観点から総合的に判断されます。それぞれの観点で良い評価を得ることが、内申点アップのポイントです。以下に、各観点ごとの具体的な対策を紹介します。
2. 「知識・技能」を高めるための対策
「知識・技能」の観点は、簡単に言えば、授業で学んだ内容をしっかり覚え、理解し、活用できるかが問われます。
定期テストや小テストでは、「知識の暗記を問う問題」と「応用的に考えて解く問題」の両方が出題されます。これらにバランスよく対応できているかどうかが評価の基準になります。
例えば、数学の文章題で、途中まで正しく解いていたものの計算ミスをしてしまった場合でも、部分点が与えられることがあります。このように、しっかり考えて解いた痕跡があれば、一定の評価は得られます。
ただし、基本的にはテストで一定の点数を取ることが前提です。テストの得点が低すぎると、「知識・技能」の評価は上がりません。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| ・暗記問題や基礎的な計算問題だけでなく、応用問題や記述問題にも対応できる力をつけましょう。 |
| ・定期テストでは、配点の高い大問で得点を重ねることが重要です。 |
| ・単なる暗記に頼るのではなく、ワークや問題集を何度も解き、解法パターンを身につける演習を繰り返しましょう。 |
3. 「思考・判断・表現」を高めるための対策
この観点では、身につけた知識・技能を活用して問題を解決したり、自分の考えを分かりやすく表現したりする力が求められます。テストだけでなく、授業内のさまざまな活動も評価の対象になります。
この観点は、「テストの応用問題を解く力」とも関連していますが、テストの成績以外にも、授業内の活動全般が評価に含まれる点が特徴です。
考える力や表現力を、幅広い場面で発揮することが重要です。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| ・記述問題やグラフ・資料を読み取る問題で、考えたことをしっかり説明する。 |
| ・論述・作文・小論文・レポートなどで、自分の意見を論理的に表現する。 |
| ・授業内での発表やグループディスカッションでも、自分の考えを積極的に伝える。 |
| ・技能教科(美術・音楽・技術家庭・体育など)でも、作品制作や発表で表現力を発揮する。 |
4. 「主体的に学習に取り組む態度」を高めるための対策
この観点は、いわゆる「授業態度」に関する評価です。つまり、授業や学習にどれだけ意欲的に取り組んでいるかがポイントとなります。
この観点については、テストの成績に関係なく評価されるため、学力面に自信がない人でも努力次第で得点アップが可能です。逆に、テストの点数が良くても、授業態度が悪ければ高い評価は得られません。
学校は、学習に向かう姿勢や態度を非常に重視しています。学力だけでなく、日々の姿勢にも注意を払いましょう。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| ・宿題や課題、提出物は必ず期限内に提出する。 |
| ・内容は丸写しせず、丁寧に取り組む。 |
| ・授業中は積極的に発言や発表を行う。 |
| ・授業に集中し、私語や居眠りをしない。 |
| ・わからない部分は積極的に質問するなど、学習意欲を示す。 |
| ・遅刻や欠席をしない、校則を守るなど、学校生活全般で誠実な態度を取る。 |
5. その他の内申点アップ方法
内申点を上げるには、基本的にはこれまで紹介した3つの観点(「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」)を意識して通知表の評定を上げることが大前提ですが、これ以外にも内申点にプラス評価が加わるケースがあります。
ただし、これらはあくまで「補助的な要素」であり、評定を大きく覆すほどの影響力はないため、内申点アップの「プラスアルファ」として考えておきましょう。
[英検・漢検などの資格]
一部の高校や学科では、英検(実用英語技能検定)や漢検(日本漢字能力検定)などの資格が内申点の加点要素、または合否判定の参考資料として活用される場合があります。
特に英語に力を入れている高校や学科では、英検取得者を優遇するケースが多く見られます。
一般的に、英検は準2級以上(高校中級レベル)を取得していると加点対象になることが多いため、取得のハードルはやや高めです。
また、漢検やその他の検定についても、学校によっては加点制度を導入している場合があります。
まずは、志望校の入試要項などを確認し、資格による優遇制度があるかを調べた上で、必要に応じて取得を目指すとよいでしょう。
英検取得による優遇制度についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験で英検取得は有利になる!|内申点や加点の優遇措置について」
[部活動などの成績]
内申点とは直接関係しないものの、推薦入試や特別選抜などでは、部活動や文化活動の実績が評価対象となることがあります。
特に、スポーツ・芸術・文化に力を入れている高校では、「スポーツ推薦」や「文化活動推薦」を設けているケースが多くあります。
ただし、評価対象となるのは、都道府県大会以上の実績や全国大会レベルが求められる場合がほとんどで、こちらも決して簡単ではありません。
これらの推薦制度を利用する場合は、成績や活動実績をしっかり積み重ねるとともに、中学校の顧問や担任の先生との相談が重要になります。
スポーツ推薦についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校推薦(スポーツ推薦)で進学する方法とは?」

まとめ
内申点は、高校受験で重要な役割を果たす評価の一つです。
通知表の成績だけでなく、日頃の授業態度や提出物、積極性など、日常の取り組みが大きく影響します。加えて、資格取得や部活動での実績がプラスになる場合もあります。
内申点は、日々の積み重ねで確実に上げることができるものです。受験に向けて、授業や学校生活を大切にしながら、計画的に努力していきましょう。
家庭教師のマスターでは、内申点アップに向けた中学生のフォローを行っています。ご興味のある方は気軽にご連絡ください!
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!























