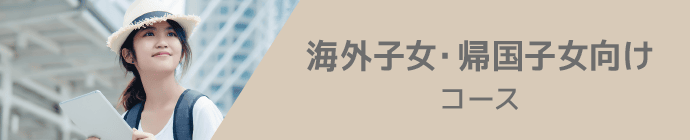帰国子女の中学受験完全ガイド|試験科目・英語対策・面接のポイントも解説
公開日:2025年4月22日

このコラムでは、帰国子女の中学受験について詳しく解説します。受験資格や試験科目の種類、求められる能力、科目別の対策法まで幅広く紹介。一般入試との違いや英語試験・面接のポイントも解説し、帰国子女枠での受験を考えるご家庭に役立つ情報をお届けします。
帰国子女入試とは?|一般入試との違い
帰国子女入試は、海外での生活経験を持つ児童を対象とした特別な入試制度です。
一般入試とは異なる出題傾向や評価基準が設けられており、帰国後の進学先を検討するご家庭にとっては重要な選択肢の一つとなります。
ここでは、帰国子女入試の目的や背景、一般入試との違い、そして帰国子女枠を設けている代表的な中学校について解説します。
1. 帰国子女入試の目的と背景
帰国子女入試の背景には、日本国内の教育制度だけでは測れない多様な経験や能力を持った児童への配慮があります。
海外での生活を通じて、言語・文化・価値観の違いに触れた子どもたちは、一般的な学力とは異なる側面で大きな強みを持っています。
文部科学省や多くの教育機関は、こうした国際的な素養や柔軟な適応力を、これからの社会で必要とされる資質と捉えています。そのため、一定の条件を満たした帰国生に対して、特別な入試枠を設けて進学の機会を広げることが目的となっています。
2. 一般入試との主な違い
帰国子女入試は、出題内容・評価基準・試験方式などの点で一般入試とはいくつかの違いがあります。帰国子女入試は、単に学力を測るだけでなく、海外経験で培った多面的な力を評価する制度です。
主な違いとして、以下のような点が挙げられます。
1. 出題科目の違い
英語力を重視する学校では、一般入試にはない英語試験が課されることもあります。
また、作文や面接を重視する学校も多く、論理的な表現力や人柄、海外経験に対する考え方などが評価対象になります。
2. 出題レベルや傾向の違い
長期間海外にいた生徒は日本語での記述に不慣れなことを想定し、国語の問題文が比較的平易に設定される場合があります。
3. 帰国子女枠を設けている主な学校
帰国子女入試を実施している中学校は全国に多数ありますが、特に首都圏を中心とした私立中高一貫校で多く見られます。
学校ごとに帰国子女の受け入れ方針や試験内容は異なるため、各校の募集要項を必ず確認することが大切です。特に受験資格や試験方式にはバリエーションがあるため、早めに調査・準備を進めておくと安心です。
以下は、代表的な学校の一部です。
渋谷教育学園渋谷中学校(東京)
帰国子女枠を設けており、英語力を活かした入試が特徴。国際的な教育にも力を入れています。
広尾学園中学校(東京)
帰国生入試を実施し、インターナショナルコースなど選択肢も豊富。多様なバックグラウンドの生徒が集まります。
洗足学園中学校(神奈川)
海外在住経験者に配慮した英語や面接中心の選抜を行っており、高い進学実績を誇ります。
同志社国際中学校(京都)
長期にわたる海外滞在者向けの帰国生入試を実施。キリスト教主義の教育のもと、国際性を重視した教育が行われています。

帰国子女入試を受験するためには?
帰国子女入試は、一般入試とは異なる基準やスケジュールで実施されることが多く、受験を検討する際には特有の準備が必要です。
受験資格の確認から出願書類の準備、スケジュール調整、さらには海外からの受験可否まで、事前に知っておくべき情報をここで詳しく解説します。
1. 帰国子女入試の受験資格
帰国子女入試の受験資格は学校によって異なりますが、一般的には次のような条件が設けられています。
・一定期間以上の海外在住歴があること(例:1年以上)
・帰国後、一定期間以内であること(例:帰国後3年以内)
このように「海外での在学期間」と「帰国からの経過期間」の両方が要件とされるケースが多いため、各校の募集要項を確認することが不可欠です。
例えば、家族帯同での滞在か、本人のみの留学かによって扱いが異なる場合もありますし、学校によっては「親の転勤による帯同」が前提となっている場合もあるため、志望校の「帰国子女の定義」を必ず確認しておきましょう。
受験資格の判断が難しい場合には、事前に検討している学校に問い合わせてみるようにしましょう。
2. 必要な出願書類とその準備方法
帰国子女入試では、一般入試よりも提出書類が多くなる傾向があります。
よく求められる書類は以下の通りです。
・海外在籍校の在学証明書・成績証明書(英文)
・パスポートのコピー(本人と保護者)
・帰国日が確認できる出入国スタンプのコピー
・保護者の勤務証明書(現地駐在の場合)
・志願理由書(日本語または英語)
・推薦状(必要な場合)
これらの書類は、日本国内の書類と違って取得に時間がかかることがあるため、早めの準備が必須です。特に、英文書類に日本語訳を添える必要がある場合や、学校の指定様式がある場合は注意が必要です。
3. 願書提出から試験までの流れと注意点
帰国子女入試の出願期間や試験日程は、一般入試より早い時期に設定されることが多くなっています。
夏頃から秋にかけて出願受付が始まり、11月〜12月に試験が行われる学校も多いため、スケジュール管理が重要になります。
出願は、オンライン出願に対応している学校も増えていますが、書類の郵送が必要な場合もあるため、郵送先や締切の確認も怠らないようにしましょう。
また、海外からの郵送には日数がかかるため、締切の「必着日」には特に注意が必要です。
4. 試験日程と帰国時期の調整ポイント
帰国子女入試を受けるにあたって、帰国時期と試験日程のバランスをどう取るかは非常に大切です。
「帰国後に国内で受験」することを前提にしている学校もあれば、「海外在住のまま受験できる」学校もありますので、以下の点に気を配ると良いでしょう。
どうしても日程調整が難しい場合は、事前に学校へ相談してみることも一つの手です。
・試験日の数か月前までには帰国し、日本の生活に慣れておく
・健康診断や予防接種など、日本で必要な手続きも余裕をもって対応する
・国内模試や対策講座に参加できるようスケジュールを確保する
5. 海外からの受験は可能?その場合の対応策
学校によっては、海外に滞在したまま受験できるよう、現地での筆記試験やオンライン面接に対応している場合があります。
・Web出願+オンライン面接のみで完結する学校
・提携校や大使館などでの試験会場受験を認めている学校
・英語エッセイ+オンライン面接のみの学校も存在
ただし、これらの受験方法が用意されているかどうかは学校によって異なるため、必ず各校の入試要項を確認し、必要に応じて直接問い合わせることが大切です。
また、時差やインターネット環境、面接の形式(Zoom、Google Meet など)についても、事前の確認・リハーサルを行っておくと安心です。

受験科目の種類と特徴は?
帰国子女入試では、一般入試と同じように筆記試験が実施される一方で、英語試験や面接など、帰国生ならではの特性を活かせる形式が取り入れられることもあります。
出題科目のパターンや評価方法は学校ごとに大きく異なるため、志望校がどのような形式を採用しているかを事前に確認することが重要です。
ここでは、主な試験科目のパターンと、それぞれの特徴について解説します。
1. 試験科目のタイプ
帰国子女入試で採用される主な試験形式には以下のようなものがあります。それぞれの型に応じて、準備のポイントも変わってきます。
4科目型(国語・算数・社会・理科)
このタイプは、一般入試と同様の形式です。特に「一般入試と同日実施」または「帰国子女入試=一般枠と同じ問題」である学校に多く見られます。
全教科バランス良く対策が必要となるため、国内受験生と同じ土俵での勝負になるケースです。帰国後のブランクがある場合は、特に社会・理科の勉強を重点的に行いましょう。
3科目型(国語・算数・英語)
このタイプは、英語力を評価に取り入れている学校でよく見られます。
帰国子女の「強み」である英語を活かせるため、国語・算数の基礎力と英語力のバランスが問われます。
英語試験の形式やレベルは学校によって異なるため、過去問やサンプル問題の確認が必要です。
2科目型(国語・算数)
このタイプが最も基本的な形式で、社会・理科の学習負担が少ない分、国語と算数に集中して対策できるので、帰国後間もない生徒でも取り組みやすいです。
ただし、国語の文章読解に慣れていない場合は、読書や問題演習を通じて語彙力や読解力を高める必要があります。
英語+α型(英語+作文など)
英語に加えて、作文やインタビュー、小論文などを課す学校もあります。
このタイプでは、論理的な表現力や自己理解の深さが重視されることが多く、日頃から自分の考えを言葉にする練習が重要です。
テーマ作文の過去問や、面接対策とあわせた準備がおすすめです。
作文書き方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「小学生のための作文書き方ガイド【作文初心者向け】|例文付き!」
学校独自型(プレゼンやグループ面接など)
プレゼンテーション、グループワーク、ディスカッション型の面接など、ユニークな選考方法が行われるケースもあります。
これらは「単なる知識」ではなく、実践的なコミュニケーション力や創造力を評価することが目的です。各学校の「教育理念」や「重視する力」が表れやすい部分なので、事前に十分な情報収集をしましょう。
2. 英語試験のレベルと対策方法
英語試験の内容・レベルは学校によって大きく異なります。
TOEFLや英検などに準じた形式を採用する場合もあれば、学校独自の読解問題や英作文が出題されることもあります。
「英語が得意だから」と安心せず、日本語との使い分けや和文英訳の練習もしておくとより安心です。
よくある出題形式
・リーディング(読解問題、内容理解)
・ライティング(エッセイ・意見文など)
・リスニング
・スピーキング(面接形式での応答)
対策のポイント
・過去問や出題例が公開されていれば必ず確認
・自分の英語力に応じた対策を行う(英検準2級〜準1級レベルが目安になることも)
・話す・書く練習を日常的に取り入れる
・英語での自己紹介や意見表明の練習も重要
3. 面接試験の内容とポイント
面接試験は、帰国子女入試で非常に重要な評価項目です。
個別面接・親子面接・グループ面接など、形式はさまざまですが、親子面接がある場合は、家庭での教育方針や帰国理由、学校への期待なども聞かれることがあるため、保護者も一緒に対策しておくことが望ましいです。
共通して見られるのは次のような項目です。
・海外生活の経験や学びをどのように捉えているか
・日本の学校生活にどれだけ適応できそうか
・志望理由や学習意欲、コミュニケーション力の有無
よくある質問例
「海外生活で印象に残っていることは?」
「なぜこの学校を志望したのですか?」
「日本の学校でやってみたいことは?」
「今までで一番がんばったことは何ですか?」
対策のポイント
・自分の言葉で、エピソードを交えて話す練習をしておく
・日本語・英語の両方で準備しておくと安心
・姿勢・目線・声の大きさなども含めた「印象」も大切
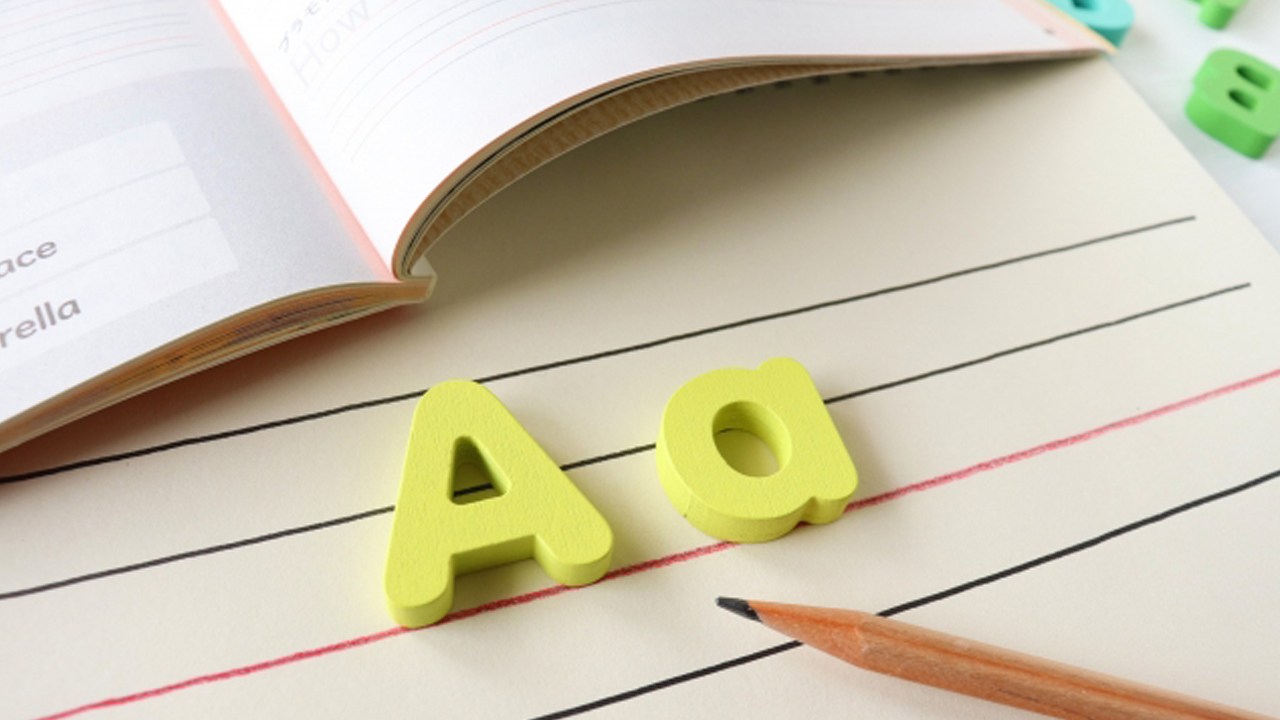
帰国子女に求められる能力とは?
帰国子女入試では、単に学力や英語力を測るだけでなく、「どのような経験を積んできたか」「それをどう活かせるか」という、より総合的な力が問われます。
多くの学校では、帰国生が持つ国際的な感覚や思考力、柔軟な対応力に期待を寄せており、そうした特性を評価する視点を持っています。
ここでは、帰国子女に特に求められる代表的な3つの能力について詳しく解説します。
1. 語学力
帰国子女の大きな強みのひとつが英語力です。
現地校やインターナショナルスクールで学んできた経験により、英語でのリーディング・ライティング・スピーキングが自然に身についている子どもも多くいます。特に英語試験や面接でこの力は大いに発揮されます。
一方で、国語力(日本語力)も重要です。
長期間海外にいた場合、日常会話はできても、読解力や記述力、語彙力に差が出ることがあります。
中学入試の国語では文章の要旨を捉えたり、考えを言語化する力が求められるため、読書・記述練習を通じて日本語の表現力も伸ばすことが必要です。
帰国子女入試では、英語力を評価する一方で、「日本語での学習にどれだけ対応できるか」も見られるため、両言語のバランスがとても大切です。
2. 異文化適応力とコミュニケーション力
帰国子女の経験は、多様な文化や価値観に触れる中で育まれた異文化適応力や柔軟な思考として表れます。
学校側もそのような国際感覚を持つ生徒に期待しており、面接や作文などでこの部分が重視されることもあります。
また、多様な環境で過ごしてきた子どもは、自分とは異なる背景を持つ相手ともスムーズに関わる力(コミュニケーション力)を持っていることが多く、それが学校生活においてもプラスになります。
そのため、面接では「現地でどんなことを感じたか」「異なる文化の中でどう対応したか」といった経験を、自分の言葉で語れることが評価につながります。
国際的な感覚を一方的にアピールするのではなく、その経験をどう活かし、どう人と関わっていきたいかを考える姿勢が重要です。
3. 論理的思考力と問題解決能力
国語・算数・作文・面接など、どの科目にも共通して求められるのが論理的思考力と問題解決能力です。これらは、与えられた情報を整理・分析し、自分の考えを筋道立てて説明したり、適切な答えを導く力のことを指します。
海外で学んだ教育スタイルの中には、「自分の意見を述べる」「正解のない問いに向き合う」といったアクティブラーニング型の授業も多く、そこで培われた力が帰国子女入試でも活かされます。
例えば作文では、テーマに対して自分なりの意見を持ち、それを根拠とともに説明する力が求められますし、面接では質問に対して考えて答える姿勢が評価されます。
算数でも、「なぜその答えになるのか」を説明できるような思考のプロセスが重視されることがあります。
このように、知識だけでなく自分の頭で考える力こそが、帰国子女入試の合格に向けた重要なカギとなります。

帰国子女入試の対策法|科目別に解説
帰国子女入試は学校ごとに試験形式や出題傾向が異なるため、志望校の特徴を把握しながら、各科目ごとにポイントを押さえた対策が必要です。また、帰国後の学習環境や日本語力のブランクを補う対策も必要です。
ここでは、頻出の5つの科目(国語・算数・英語・作文・面接)について、効果的な対策方法を紹介します。
1. 国語
帰国子女にとって最もハードルを感じやすいのが国語です。
特に長文読解や記述問題では、語彙力・文法・文脈理解など総合的な言語力が求められます。
特に、記述式の問題では筋道の通った答え方を意識することが大切です。
対策のポイント
・日常的に読書の習慣をつける(物語・説明文・論説文などジャンル問わず)
・音読と要約練習を繰り返すことで、読解と表現の力を養う
・過去問や問題集を通じて、設問の意図を読み取る練習をする
・苦手な漢字や語句は、日々の生活の中で少しずつ積み上げる
2. 算数
算数は、帰国子女でも比較的点数を取りやすい科目と言われていますが、日本式の出題形式や用語に不慣れな場合は注意が必要です。
特に、図や表を使って考える力や、解答へのプロセスを説明できるようにしておくと、記述問題への対応にもつながります。
対策のポイント
・計算力を高め、基本的な計算問題は確実に正解できるようにする
・文章題では「何を求めるか」「どんな情報が与えられているか」を整理する習慣をつける
・図形や割合、速さなど頻出単元を重点的に復習する
・日本語での問題文に慣れることも重要な練習の一つ
3. 英語
英語は帰国子女の得意分野とされることが多いですが、試験内容に応じた対策が求められます。
リーディング・ライティング・リスニング・スピーキングと、総合的なスキルが求められることもあるため油断は禁物です。
また、出題傾向によっては、TOEFL Juniorや英検の勉強がそのまま対策になることもあります。
対策のポイント
・過去問・サンプル問題があれば形式や難度を確認する
・意見文・エッセイなどライティングの型を身につける(導入→主張→理由→結論)
・リスニング対策は、英語のアニメやニュースなどを活用して日常的に耳を慣らす
・スピーキングは、日記や出来事を英語で話す練習を日常的に行うと効果的
4. 作文
作文は、自己表現や論理的な思考力を測る重要な科目です。
帰国子女向け入試では「海外での経験」や「自分の考え」を問われることが多く、自分の言葉で語れる力が試されます。
作文は「書き慣れ」が大切なので、週1回でも良いので定期的に書く習慣をつけておくと安心です。
対策のポイント
・よくあるテーマ(経験・家族・夢・学校生活など)について、自分の意見を書いてみる
・構成を意識して練習(起承転結、もしくは「結論→理由→具体例→まとめ」)
・語彙や表現を増やし、文法ミスを減らす練習も合わせて行う
・添削を受けることで、自分のクセやミスに気づくのも有効
5. 面接
面接は、受験者の人柄や考え方、適応力などを直接見られる場です。
質問への答え方だけでなく、態度や言葉遣い、表情など全体の印象も評価に含まれます。
特に帰国子女の場合、「海外での経験をどう感じているか」「日本でどんな学校生活を送りたいか」といったテーマがよく出されるため、自分の体験と考えを結びつけて話せるようにしておくことがカギとなります。
対策のポイント
・頻出質問(志望理由・海外生活の印象・将来の夢など)に答えられるよう準備
・練習は「内容」だけでなく「声の大きさ・姿勢・目線」も意識
・親子面接がある場合は、保護者とのやり取りもシミュレーションしておく
・緊張しすぎず、自分の言葉で話すことを心がける

まとめ
帰国子女入試は、海外での経験や語学力を活かせる特別な入試制度です。一般入試とは異なる特徴があるため、早めに情報を集め、学校ごとの試験内容や出願条件をよく確認することが大切です。
自分の強みを理解し、科目ごとの対策をしっかり行えば、帰国子女ならではの力を発揮できるはずです。お子さまが自信を持って受験に臨めるよう、計画的な準備を進めていきましょう。
オンライン家庭教師のマスターでは、海外子女・帰国子女向けの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【海外子女・帰国子女向けコース】について
オンライン家庭教師のマスターについて
オンライン家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 学校の授業や教科書・ワークのサポート
- 定期テストのサポート
- 中学・高校・大学受験のサポート
- 進学塾の補習
- 不登校のお子さんのサポート
- 発達障害のお子さんのサポート
- 小論文や作文のサポート
- 英検・漢検・TOEIC対策のサポート
など、ご家庭のニーズに沿った内容を指導しています。
ご家庭にある問題集やプリントで、生徒さんが教えてほしい問題や分からない分野を教えます。
料金について
「家庭教師は料金が高い」といったイメージを持つ方は多いのではないでしょうか?
オンライン家庭教師のマスターは、多くのオンライン家庭教師会社よりも低料金で指導を受けることができるので、是非、他社料金と比較してみてください!
また、2人同時指導のお得なプランもご提供しています。
- 中学1〜2年生:9,200円~/月
- 中学3年生:9,750円~/月
- 小学1~3年生:7,950円~/月
- 小学4~6年生:8,500円~/月
- 中学受験:11,700円~/月
- 高校生:11,640円~/月
- 2人同時指導(ペアレッスン):3,990円~/月
兄弟姉妹やお友達と一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、お得な料金でオンライン家庭教師の指導が受けられます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
また、オンライン家庭教師のマスターは、業界最大級の登録家庭教師の中から厳選された教師を選抜しています。お住まいの地域にかかわらず、低料金で高品質の指導を受けることができます。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学・地学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目全ての指導が可能です。
また、定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
オンライン家庭教師のマスターでは、お子さんの目的に合わせた様々なコースをご用意しています。
さらに、お子さんの学力・進路・現在の状況などに合わせて、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムを組み、指導を行います。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たちオンライン家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
オンライン家庭教師のマスターでは、実際に担当する家庭教師による無料体験レッスンを行っています。
・オンラインでの指導はどんな感じか?
・先生の教え方は分かりやすいか?
・先生の人柄や子どもの相性は合っているか?
などを是非体験してみてください!
ご興味のある方は、下記より気軽にお問合せください。