勉強しない中学生をやる気にさせる方法|親の関わり方とNG行動も解説
公開日:2025年3月27日
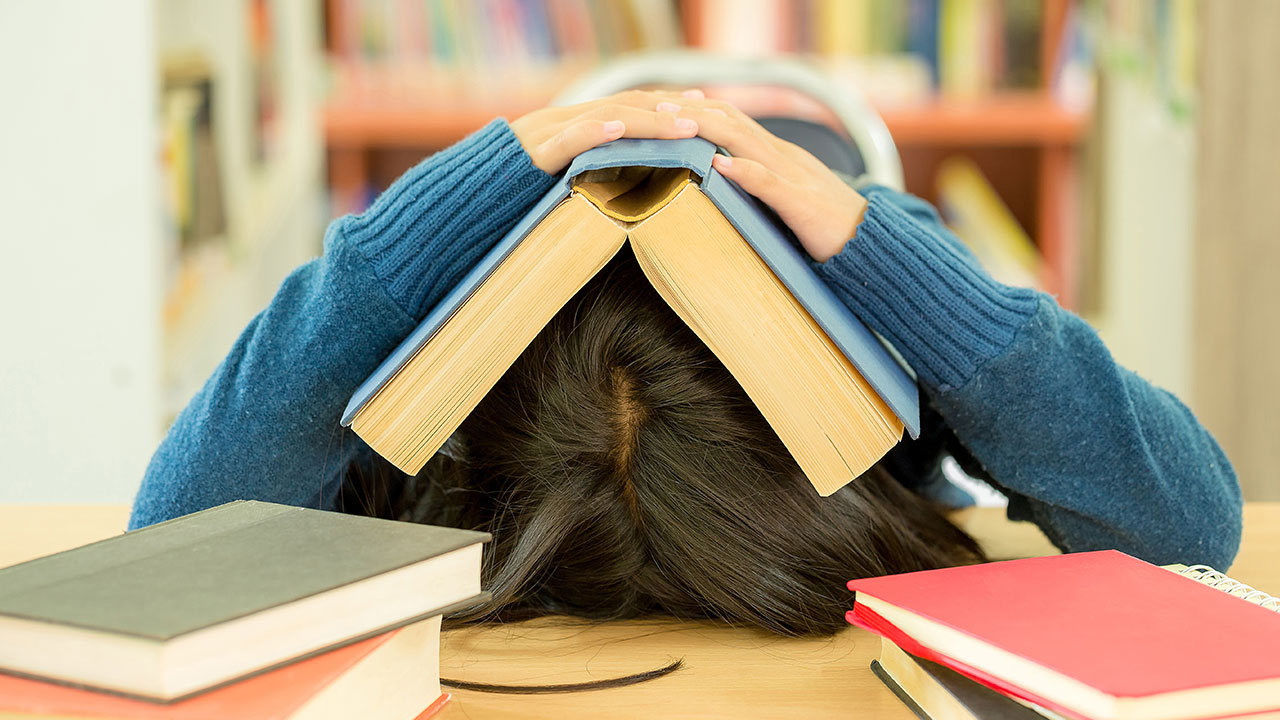
中学生になると、様々な理由で勉強をしなくなる子どもが増えます。このコラムでは、中学生が勉強しなくなる理由、やる気を引き出すための解決策、やる気を奪う親のNG行動について詳しく解説します。子どもの勉強嫌いで悩んでいる保護者の方は、ご一読ください。
中学生が勉強しない7つの理由
中学生になると、様々な理由で勉強をしなくなる子どもが増えます。このコラムでは、中学生が勉強しなくなる理由、やる気を引き出すための解決策、やる気を奪う親のNG行動について詳しく解説します。子どもの勉強嫌いで悩んでいる保護者の方は、ご一読ください。
1. 勉強することの重要性が分かっていない
中学生は、まだ「勉強する意味」をしっかり理解できていないことが多く、「将来の自分のため」と言われてもピンときません。「こんなことを覚えて何の役に立つの?」「何のために頑張らないといけないの?」という疑問を抱えたままでは、やる気はなかなか湧いてきません。目的意識が曖昧なまま勉強しても、気持ちは上の空になりがちです。
2. 授業についていけない、勉強方法がわからない
中学の勉強内容は一気に難しくなります。小学校の延長のような感覚でいると、すぐに授業についていけなくなります。
「わからない=やりたくない」と感じるのは自然な反応です。また、効率のよい勉強方法が身についていないと、いくら頑張っても成果が出ず、どんどんやる気を失ってしまいます。
3. 友達や家族の影響
周囲の環境も、子どもの勉強意欲に大きく影響します。
特に思春期は、友達からの影響力が非常に強くなる時期なので、仲の良い友達が勉強に対して消極的だったりすると、「自分も別にやらなくてもいいや」という空気に流されてしまうことがあります。
また、家族が勉強や成績、進路などの話をあまりしなかったりすると、勉強に対する関心が薄れてしまいます。
4. スマートフォン(ゲームやSNS)への熱中
現代の中学生にとって、スマートフォンやオンラインゲーム、SNSは日常生活の中心になりつつあります。
すぐに楽しさや刺激を得られるこれらのツールは、地道な勉強よりも遥かに魅力的に映ります。「気づけば何時間もスマホをいじっていた」ということが習慣化すると、勉強の時間はどんどん奪われてしまいます。
子どものゲーム・ネット依存についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもがゲーム・ネット依存になってしまう要因と解決策とは?」
5. 生活リズムの乱れ(夜更かし、部活が忙しい)
部活や習い事で忙しかったり、SNSや動画を見ることで、夜遅くまで起きている生活が続くと、疲れや眠気で勉強どころではなくなります。
また、夜更かしが習慣化すると朝起きられず、学校でもボーっとしてしまい、授業への集中力が低下します。生活リズムの乱れは、勉強に向かう気力を根本から奪ってしまいます。
昼夜逆転の治し方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「昼夜逆転の治し方|不登校、引きこもり、ゲーム・ネットのやり過ぎの子ども」
6. 達成感や成功体験が少ない
やる気は、成功体験の積み重ねによって育つものです。ですから、努力しても結果につながらないと、「どうせやっても無駄」という気持ちが強くなります。
勉強で上手くいった経験が少ないと、「自分は勉強ができないから…」と諦めてしまい、勉強への苦手意識が定着してしまいます。
7. 反抗期
中学生は自立心が芽生え、親の指示に素直に従うのが難しくなる時期でもあります。
「勉強しなさい」と言われると反発したくなるのは、反抗期の自然な反応です。親の言葉に逆らいたいという気持ちが先に立ち、勉強する意欲があっても、表面的にはやろうとしない態度になってしまうことがあります。
反抗期についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説」

中学生に勉強をさせる8つの解決策|やる気を引き出す親の関わり方
子どもが勉強をしないのには理由があります。そして、その理由を理解した上で、適切にアプローチすれば、やる気は自然と育っていきます。
無理に机に向かわせるのではなく、「自分からやりたい」と思えるようなサポートこそが、保護者にできる最大の後押しです。
ここでは、家庭で実践できる8つの解決策を、より詳しくご紹介します。
1. 「小さな成功体験」を積ませる
勉強へのやる気は、「できた!」という体験が土台になります。ですから、まずは「簡単すぎるくらいの目標」から始めることがポイントです。
例えば、
「英単語を3個だけ覚えてみよう」
「計算問題を1ページだけ解こう」
というように、「それならできるかも!」と思える範囲に目標設定します。そして終わったら、「お、やったね!」「いいじゃん、進んだじゃん!」とすぐに声をかけてあげてください。この「すぐ褒められるという経験」が、子どもに「やればできる」という手応えを感じさせ、次へのやる気を生み出します。
2. 「勉強の意味」を一緒に考える
「なんで勉強しなきゃいけないの?」と聞かれたとき、親が一方的に「将来のため」「いい高校に行くため」と言っても、子どもには響かないことが多いです。ですから、本人の価値観に合った意味づけを一緒に考えることが大切です。
例えば、こんな会話が効果的です。
「最近、どんな授業が面白いと思った?」
「○○が好きなんだね。それって△△を勉強していけば、もっと詳しくなれるよね」
「これができたら、自分で選べる学校や職業が増えてくるんだよ」
「勉強=辛いこと」というイメージを変えていくためにも、ポジティブな視点で会話することを意識しましょう。
3. 勉強計画を一緒に立てる
「何をやればいいか分からない」「量が多すぎてやる気が出ない」
そんな時は、親が勉強の設計士のような役割を果たすと、子どもは安心して勉強できるようになります。
具体的には、
「今日はこの5問だけ解こう。時間は20分以内」
「夕食前に暗記、夕食後にワークを1ページ。これでOKにしよう!」
というように、量と時間の枠を作ってあげるのがコツです。
さらに「この時間だけは集中、終わったら好きなことしていいよ」と、小さなご褒美をセットにするのも効果的です。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」
4.「成果」ではなく「努力」を認める
テストの点数や成績だけで子どもを評価していると、プレッシャーがかかりすぎてやる気を失ってしまいます。大切なのは、結果ではなく努力に注目することです。
例えば、
「この前より早く解けるようになったね!」
「コツコツ続けてるの、ちゃんと見てるよ!」
「わからないところを調べようとしたの、偉いね!」
など、過程や取り組みの姿勢に目を向けて褒めることで、子どもは「見てくれてる」と感じ、次も頑張ろうと思えるようになります。
5. 子どもと一緒に何かに取り組む
「勉強しなさい」と一方的に命令するのではなく、親も共に頑張る姿勢を見せることも効果的です。
例えば、
「お母さんも本読むから、一緒に静かな時間にしよう」
「お父さんも資格の勉強してるから、同じ時間でやろうか?」
「この問題、ちょっと一緒に考えてみようか?」
といった具合に、子どもが孤独を感じないように関わることが大切です。「一緒に頑張ってくれる人がいる」と思えることで、安心感とやる気が生まれます。
6. 適度に声をかける
「うるさく言いすぎると反発する」かと言って「何も言わないと放っておくことになる」。
このバランスを取ることが難しい所ですが、気にかけているという姿勢をさりげなく示す声かけがポイントです。
例えば、
「さっき集中してたよね、すごいな〜と思ったよ」
「あの問題、難しそうだったけど進んだ?」
「疲れてたら休んでもいいけど、手伝えることあったら言ってね!」
など、子どものペースを尊重しつつ、優しく見守る声かけが有効です。タイミングは、勉強が終わった直後や、休憩中などがベストです。
7. 学習環境を整える
集中できる場所があるかどうかは、やる気に直結します。
机の上が散らかっていたり、テレビの音が聞こえる部屋では、嫌でも集中力が途切れてしまいます。
親ができるサポートとしては、
・机の上を一緒に片づける
・スマホやゲームは別の部屋に置くルールを決める
・照明やイスの高さを見直す
といった工夫で、「ここなら勉強に集中できる」と思える場所を用意することが大切です。学習環境を整えるだけでも、自然と勉強へのハードルが下がります。
8. 必要に応じて、家庭教師・塾などを検討する
「親子だからこそうまくいかない」こともあります。親の声が届かない時に、第三者に頼ることは決して甘えではありません。
・苦手な教科だけ週1回家庭教師をつける
・自習室を活用できる塾に通わせて、勉強の習慣を身につける
・「お兄さん・お姉さん的な存在」として接してくれる講師に出会う
このような学習環境は、子どもが客観的に自分を見直すきっかけにもなります。もちろん、子どもの気持ちを尊重し、無理に通わせるのではなく、一緒に話し合って決めることが大切です。
塾と家庭教師についてもっと知りたい方はこちら
⇒「塾と家庭教師どっちがいいの?|どちらが子供に合うか徹底検証!」
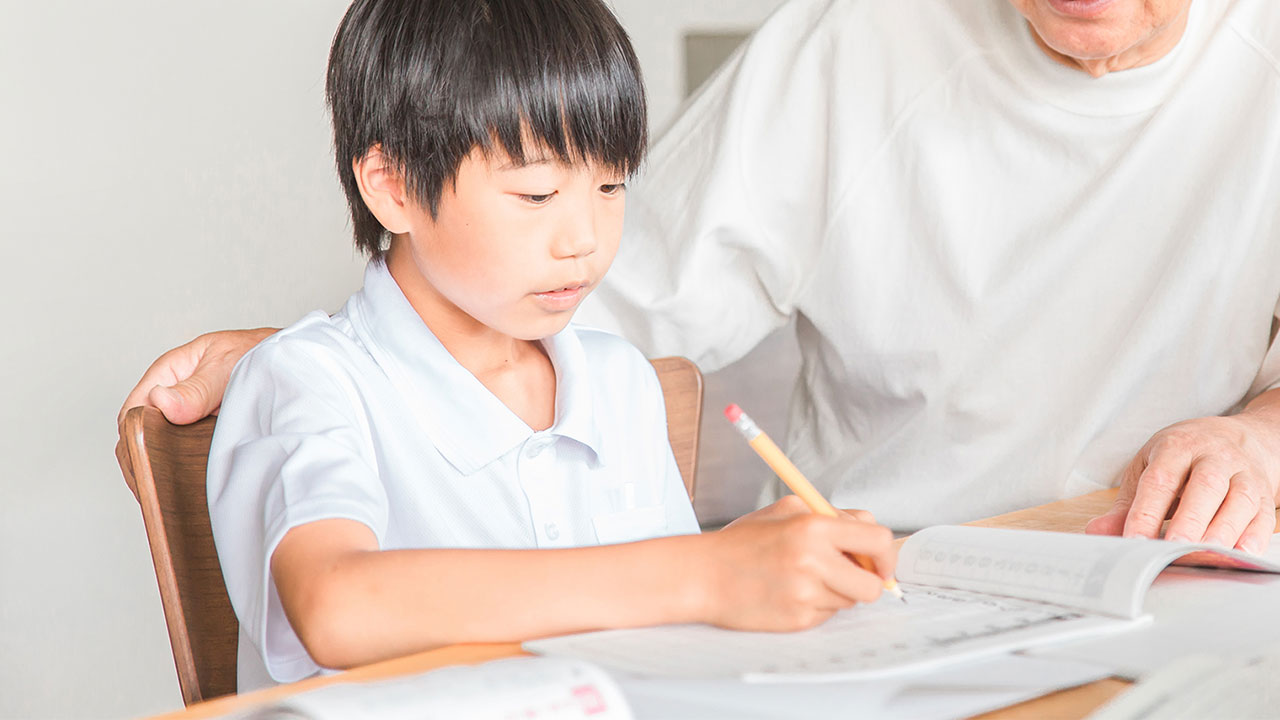
中学生のやる気を奪う親の7つのNG行動
子どもに「勉強してほしい」と思うあまり、知らず知らずのうちにやる気を下げるような行為を親がしてしまっていることがあります。
中学生は思春期に入り、親の言葉や態度に敏感な時期です。親の接し方ひとつで、子どもの勉強への姿勢がガラリと変わることも少なくありません。
ここでは、特に注意したいNG行動を7つ紹介します。思い当たる点がないか、一度振り返ってみましょう。
1. 「勉強は将来役に立たない」といった話をしてしまう
つい大人の本音で「勉強なんて社会に出たら使わないよ」などと言ってしまうことがありますが、これは子どもの学習意欲を一気に奪ってしまうNGワードです。
親がそんな風に思っているなら、「勉強なんてやらなくていいんだ」と受け止めてしまうのも当然です。
冗談半分や本音ではなくとも、「勉強=意味がないこと」という印象を植え付けてしまうため、絶対に避けるべき言動です。
2. 「なんでやらないの?」と責める
「どうしてまだ宿題やってないの?」「なんでそんなにダラダラしてるの?」という言葉は、子どもにとって「責められている」と感じやすいです。
子どもも中学生になると、自分でも「やらなきゃいけない」と思っていることが多く、責められることで、罪悪感が怒りに変わって反発することがあります。
やらないことを問い詰めるよりも、「何からやるか一緒に考えてみようか?」といった共に解決する姿勢が大切です。
3. 「勉強しなさい!」と命令口調で勉強を強制する
親が強く言えば言うほど、子どもは「自分の意志ではなく、やらされている」と感じてしまい、勉強に対する拒否反応が強まります。
「今すぐやりなさい!」「スマホはもう没収!」といった言葉で追い詰めると、一時的にやったとしても、自発的なやる気にはつながりません。
重要なのは、“自分でやろう”と思わせるように関わることです。強制よりも、信頼と対話をベースにしましょう。
4. 本人の自主性に任せ過ぎる
一方で、「本人がやる気になった時にやればいい」と完全に任せっきりにしてしまうのも問題です。
親からの関心が感じられないと、「どうせ誰も見ていないし」「やってもやらなくても、どっちでもいいんだ」と感じ、モチベーションが下がってしまいます。自立を促すことは大切ですが、子どもが困ったときに助けを求められる距離感は保っておきたいものです。無関心ではなく、見守る姿勢が大切です。
5. 他の子と比べる
「〇〇ちゃんはもっとできてるよ」「お兄ちゃんはその頃には…」という比較は、子どもの自尊心とやる気を深く傷つけます。
比べられることで、「自分はダメなんだ」と感じてしまい、努力する意欲そのものが失われてしまうのです。
誰かと比べるのではなく、「昨日の自分」と比べて前進したことを見つけてあげると、前向きな気持ちが育ちます。
6. 結果だけを重視して褒めたり叱ったりする
テストの点数や成績にばかり注目すると、「勉強=点数を取るためのもの」という誤った意識が生まれてしまいます。
「90点なら褒めるけど、70点ならダメ」では、子どもは努力より結果ばかり気にするようになるので、勉強が不安やストレスの原因になります。結果が良くても悪くても、「よく頑張ったね」「ここまでやれたのはすごいよ」と、プロセスを認める姿勢が大切です。
7. 勉強の邪魔になる行動をする
子どもが頑張って勉強している時に、家族の誰かがすぐ隣でテレビを観ていたり、スマホゲームに夢中になっていたりすると、「なんで自分だけ我慢してるの?」という不公平感を感じてしまいます。
特に思春期の子どもは、親の言動に敏感です。自分も大人と同じように自由に過ごしたい気持ちが強くなるため、目の前で親がリラックスしていると、勉強への集中が切れてしまいます。
親も全てを我慢する必要はありませんが、「ちょっと離れた場所で過ごす」「勉強が終わったら一緒にテレビを観ようね」など、勉強している子どもに配慮する態度を見せることが重要です。

まとめ
中学生が勉強しないのには、理由があります。そして、頭ごなしに叱るのではなく、やる気を引き出す関わり方を意識することで、子どもは少しずつ変わっていきます。
大切なのは、結果を急がず、子どもの努力や気持ちに寄り添うこと。親の声かけや環境づくり次第で、勉強に向かう姿勢は確実に変わります。
焦らず、否定せず、応援する姿勢がやる気の土台になります。
家庭教師のマスターでは、やる気の出ない中学生への学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























