ポイントを押さえたノートまとめ方のコツ|小中学生向け簡単ノート術!
公開日:2025年3月18日
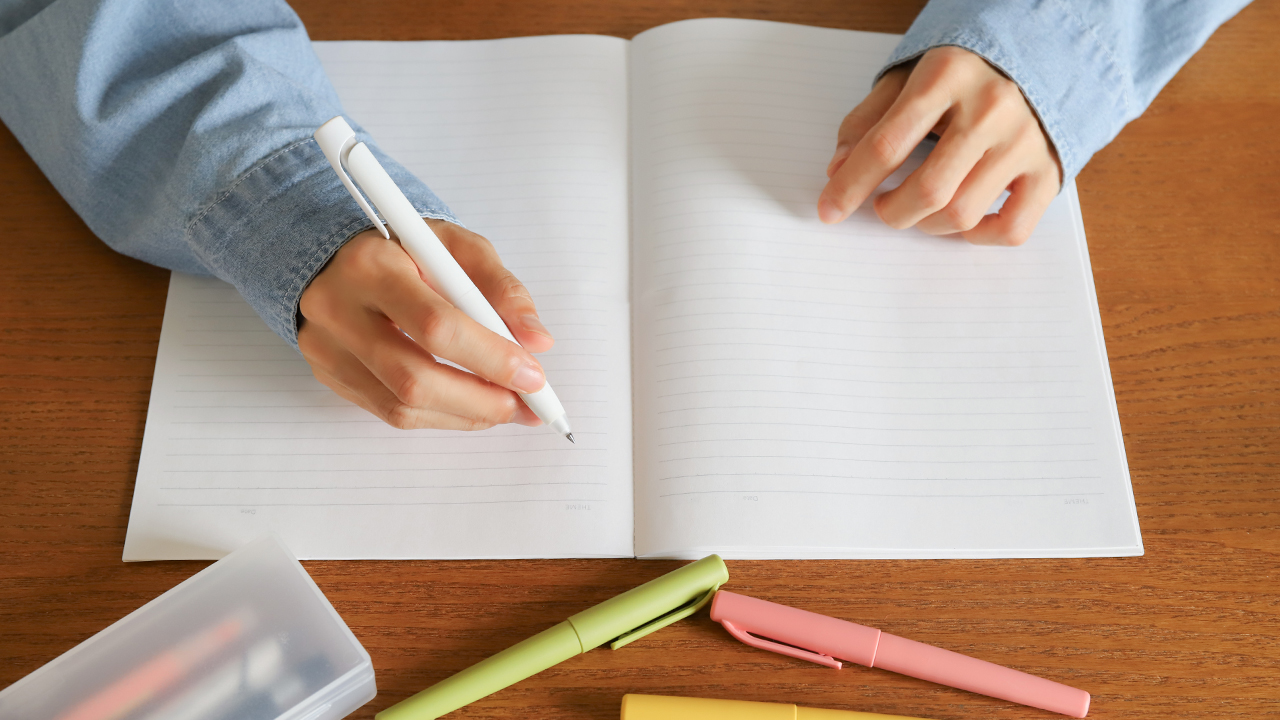
授業の予習・復習をする上でノート作りは重要なポイントです。
このコラムでは、小中学生の方に向けて、ノートの基本的な取り方、効果的なノートのまとめ方、やってはいけないノートのまとめ方について詳しく解説します。是非参考にしてみてください!
ノートの取り方の基本ポイント
授業で学んだことをしっかりと定着させるためには、ノートの取り方がとても重要です。
ただ黒板を書き写すだけではなく、ポイントを押さえたノートを作ることで、復習がしやすくなり、理解も深まります。
ここでは、小中学生向けに簡単に実践できるノートのまとめ方のコツをご紹介します。
1. 日付・タイトル・教科書のページを書く
ノートを取るときには、まず日付、タイトル、教科書のページを明記することが大切です。
日付を書くことで、後から見返したときに、どの授業の内容なのかを把握しやすくなります。また、テスト前に復習をするときも、どの単元をいつ学習したのかがすぐに分かるため、効率的に復習できます。
タイトルをつけることも重要です。授業のテーマを明確にしておくことで、ノートの内容を整理しやすくなり、必要な情報を素早く見つけられます。
さらに、教科書のページを書いておくと、ノートだけでなく教科書を併用しながら学習できるため、知識を深めるのに役立ちます。
2. フォーマット(見出し、構成)を統一する
ノートの書き方が毎回バラバラだと、後から見返したときに分かりにくくなってしまいます。そのため、フォーマットを統一することが大切です。
例えば、タイトルや見出しを大きめに書くことで、授業のテーマをすぐに把握できるようになります。
本文の書き方にも一定のルールを決めておくと、ノートが整理されて分かりやすくなります。例えば、大事なポイントは赤ペンで書く、説明部分と結論部分を分けて記述する、重要な情報は囲みをつけるなどの工夫をすると、見やすいノートになります。
また、情報を整理しやすくするために、箇条書きや段落分けを意識すると、より分かりやすくなります。
3. 黒板に書かれたことを板書する
授業中に先生が黒板に書いた内容は、特に重要なポイントが含まれています。
黒板の内容をノートに書き写すことは基本ですが、ただ書き写すだけでなく、内容を整理しながら書くことが大切です。
例えば、見出しや段落をつけて、何が重要なのかを分かりやすく整理すると、後から復習しやすくなります。計算問題や図、グラフなども忘れずに書き写すことで、視覚的に理解しやすくなります。
また、先生が口頭で説明したこともメモしておくと、より深い理解につながります。
4. 余白を適度に空ける
ノートをぎっしりと埋めてしまうと、後から見直したときに読みにくくなってしまいます。適度な余白を空けることで、情報が整理され、視覚的にも分かりやすくなります。
例えば、ノートの端に余白を作ることで、後から追加のメモを記入しやすくなります。また、重要なポイントごとに少し間を空けておくことで、どの部分が特に大切なのかが分かりやすくなります。
復習の際に気づいたことや、授業後に先生が補足説明した内容を追記できるように、メモ欄を確保しておくのもおすすめです。
5. 重要な部分を強調する
ノートの中で特に重要な部分を強調することで、どこがポイントなのかをひと目で判断しやすくなります。
強調する方法はいくつかありますが、例えば、色ペンを使って大切な言葉を目立たせると、後から復習する際に重要なポイントがすぐに分かります。また、アンダーラインを引いたり、マーカーで囲んだりすることで、強調したい部分を分かりやすくすることもできます。さらに、記号を活用することで、ノートの情報が整理されやすくなります。
ただし、あまりにも色やマークを多用しすぎると、かえってノートが見づらくなってしまうため、バランスを考えて工夫することが大切です。
6. 先生の話をメモする
黒板の内容をノートに書き写すことも重要ですが、それだけでは十分ではありません。
先生が授業中に口頭で説明する内容の中には、テストに出る可能性が高いポイントや、より深い理解につながる情報が多く含まれています。そのため、先生の話をメモする習慣をつけることが大切です。
すべてを書き取るのは難しいですが、キーワードや簡単な要点だけでもメモしておくと、復習の際に役立ちます。
また、略語を使ってメモを取ることで、素早く記録することができます。例えば、「例→」や「重要→」などの簡単な記号を使うと、短い時間で必要な情報をまとめることができます。
ノートの余白を活用して、後で補足できるようにしておくと、より分かりやすいノートになります。

効果的なノートのまとめ方6選
ノートを上手にまとめることで、復習の効率が上がり、学習内容の理解が深まります。ただ書くだけでなく、目的を意識しながら工夫することで、後から見返したときに役立つノートを作ることができます。ここでは、効果的なノートのまとめ方を6つ紹介します。
1. 目的(何のためにまとめるのか?)を明確にする
ノートをまとめる際に、まず「何のためにこのノートを作るのか」をはっきりさせることが大切です。
例えば、授業の内容を整理するためのノートなのか、テスト勉強用のノートなのか、あるいは自分が理解を深めるためのノートなのかによって、書き方が変わります。
授業中に取ったノートを後から見直すためなら、できるだけ分かりやすく整理することが重要です。一方で、テスト前に復習するためのノートであれば、試験に出そうなポイントを中心に要点を絞って書く方が効果的です。
目的を意識することで、ノートの作り方が明確になり、無駄なく活用できるようになります。
成績が上がるノートの取り方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「成績が上がるノートの取り方|上手なノートづくりのポイントとは?」
暗記ノートについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「暗記ノートの作り方|小中高生のための簡単作り方ガイド」
2. タイトルと見出しを揃える
ノートを分かりやすくまとめるためには、タイトルと見出しを統一することが大切です。
毎回、ノートの上部にタイトルを書き、その下に見出しを整理して書くことで、情報がスムーズに整理され、後から見返しやすくなります。
例えば、数学のノートであれば「方程式の解き方」「比例と反比例」などのタイトルをつけ、その下に詳しい説明や例題を書くと、内容が明確になります。
また、見出しの大きさや書き方を統一することで、視覚的にも整理され、どこに何が書いてあるのかがひと目で分かるようになります。
3. 箇条書き・記号を使う
長い文章をそのまま書くと、情報が埋もれてしまい、重要なポイントが分かりにくくなります。
そのため、箇条書きを活用して、要点をコンパクトに整理することが効果的です。
また、記号を使うことで、さらに分かりやすくまとめることができます。例えば、「・」を使って項目を並べることで、情報が見やすくなりますし、「→」を使うことで、因果関係や流れを整理することもできます。
「※」や「★」などの記号を使って重要なポイントを強調するのもおすすめです。
ただし、多くの種類の記号を使いすぎると逆に見づらくなるため、使う記号の種類はある程度統一することが大切です。
4. 色分けで情報を視覚的に整理する
ノートを分かりやすくするためには、色分けを活用するのも有効です。
ただし、あまりにも多くの色を使いすぎると、かえって情報が散らかってしまうため、使う色を絞ることがポイントになります。例えば、「黒で通常の文字を書く」「赤で特に重要なポイントを強調する」「青で補足説明を書く」など、色ごとに役割を決めておくと統一感が生まれます。
また、緑や黄色を使って注意点を目立たせると、より分かりやすいノートになります。
ただし、色を使いすぎると逆にごちゃごちゃしてしまうため、3色程度に抑えるのが理想的です。
5. 図や表を活用する
文章だけでノートをまとめると、どうしても情報が長くなり、理解しにくくなることがあります。そのため、できるだけ図や表を活用することで、情報を整理しやすくなります。
例えば、理科や社会のノートでは、グラフや地図を取り入れると、視覚的に分かりやすくなります。また、数学の公式や計算手順を表にまとめることで、ポイントを整理しやすくなります。
授業で配られたプリントや資料をコピーして貼り付けるのも一つの方法です。特に、細かい説明が書かれた資料をそのままノートにまとめるのが大変な場合は、コピーを取ってから補足を書き足すことで、無駄なくノートを整理することができます。
6. 科目別にまとめ方を工夫する
すべての教科で同じノートの取り方をするのではなく、科目ごとに適した方法を取り入れることが大切です。
例えば、数学のノートでは、問題と解答をセットで書くことで、解き方を復習しやすくなります。
社会や理科では、年表や図を活用して、情報を整理するのが効果的です。
英語の場合は、単語リストを作ったり、例文を書いたりすることで、記憶に定着しやすくなります。
国語では、登場人物の関係図や、文章の要点をまとめると、読解がしやすくなります。
このように、教科ごとに工夫しながらノートをまとめることで、より効率的に学習を進めることができます。

やってはいけないノートのまとめ方7選
ノートをしっかりとまとめることは学習においてとても大切ですが、間違ったやり方をしてしまうと、せっかくの努力が無駄になってしまいます。見やすく分かりやすいノートを作るためには、やってはいけないポイントを知り、それを避けることが重要です。
ここでは、学習効果を下げてしまうノートのまとめ方の間違いを7つ紹介します。
1. 板書や教科書を丸写しする
ノートを取る際に、黒板の内容や教科書の文章をそのまま書き写すだけでは、学習の効果が低くなってしまいます。
授業の内容をただ記録するだけではなく、ポイントを理解しながら書くことが大切です。重要な部分を抜き出したり、自分の言葉で要約したりすることで、学んだことを整理しやすくなります。
また、先生の説明を聞きながら、必要な補足情報をメモすることで、より理解が深まります。
ただの書き写しではなく、考えながらノートをまとめることを意識しましょう。
2. 文字を詰め込みすぎる
ノートをきれいにまとめようとして、ページいっぱいに文字を書いてしまうと、後から見返したときにとても読みにくくなってしまいます。
余白を適度に残し、情報を整理しながら書くことが大切です。特に、あとで補足を加えたいときや、復習時にメモを追加したいときのために、余裕を持たせた書き方をすることが重要です。
読みやすいノートにするためには、適度にスペースを空け、重要な部分が目立つように工夫するとよいでしょう。
3. 長文で書きすぎる
ノートを詳しくまとめようとするあまり、すべての内容を長文で書いてしまうと、情報が埋もれてしまい、重要なポイントが分かりにくくなります。
特に、復習の際にすばやく要点を確認したいときに、長い文章ばかりでは時間がかかってしまいます。簡潔にまとめることを意識し、キーワードや短いフレーズで記録するようにすると、効率よく復習できます。
必要な部分だけをコンパクトに書くことで、ノートの情報が整理され、見やすくなります。
4. 色を使いすぎる
ノートを分かりやすくするために色分けをするのは有効な方法ですが、あまりにも多くの色を使いすぎると、逆にごちゃごちゃしてしまい、どこが大事なのか分かりにくくなってしまいます。
色を使うときは、重要なポイントを目立たせるために適度に使うことが大切です。
例えば、黒で通常の文字を書き、赤で特に重要なポイントを強調し、青で補足説明を書くなど、色の役割を決めておくとよいでしょう。色を3色程度に抑えることで、統一感のあるノートになります。
5. きれいに書くことを優先しすぎる
ノートをきれいにまとめようとしすぎると、時間がかかりすぎてしまい、肝心の学習の効率が下がってしまうことがあります。
もちろん、見やすいノートを作ることは大切ですが、それ以上に重要なのは、学習内容をしっかり理解し、復習しやすくすることです。書くことに集中しすぎて授業の説明を聞き逃してしまったり、まとめることに時間をかけすぎて勉強時間が不足してしまったりするのは本末転倒です。
ノートは完璧にきれいにする必要はなく、後で見直して分かりやすければ十分です。
6. 1回まとめて終わりにしてしまう
ノートをまとめた後、それを見返さずに終わってしまうと、せっかくの努力が無駄になってしまいます。
ノートは一度書いたら終わりではなく、何度も見返してこそ意味があるのです。授業で取ったノートをもとに、あとで復習ノートを作ったり、テスト前に見直して重要な部分をチェックしたりすることで、学習効果が高まります。
特に、時間が経つと忘れてしまうことも多いので、定期的にノートを振り返る習慣をつけることが大切です。
7. どの科目も同じようにまとめる
すべての科目で同じ方法でノートをまとめるのは、あまり効率的ではありません。
例えば、数学では計算過程を詳しく書いた方が理解しやすいですが、社会では年表や地図を活用した方が分かりやすくなります。また、英語では単語や文法のポイントを整理することが重要ですが、国語では登場人物の関係や要点をまとめることが効果的です。
科目ごとに適したノートのまとめ方を考え、最も理解しやすい形で整理することが大切です。
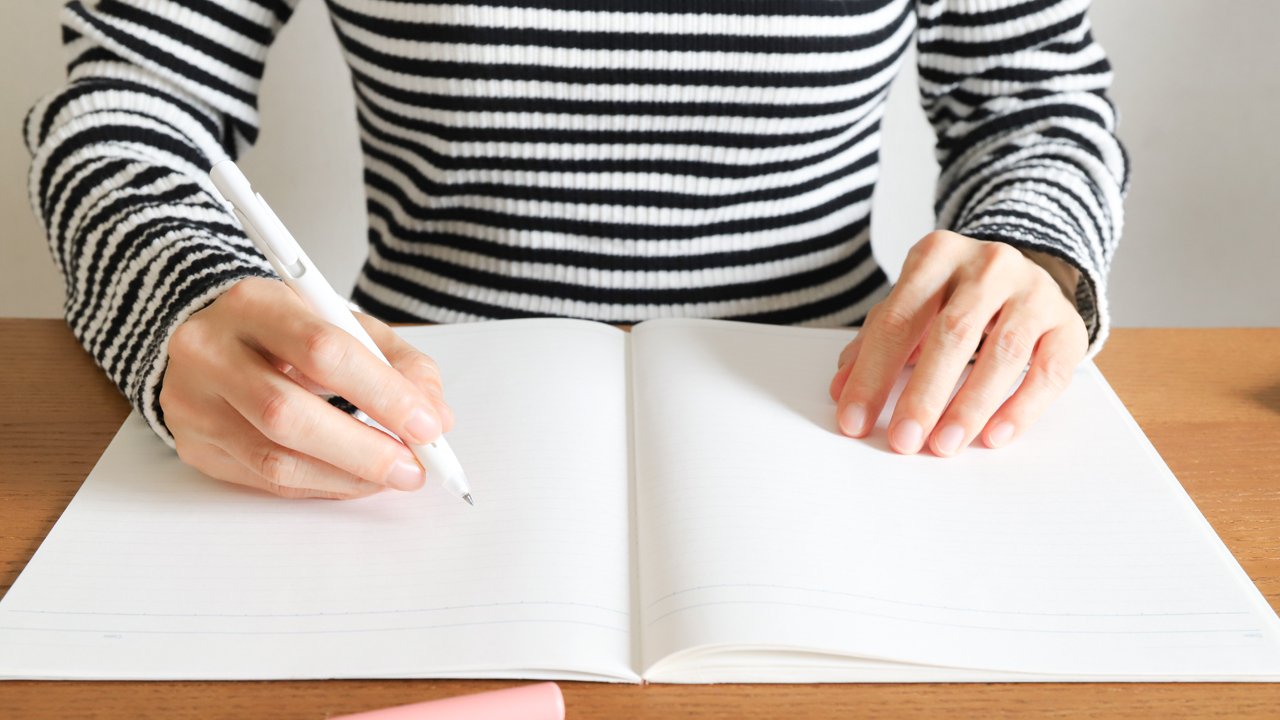
まとめ
ノートの取り方やまとめ方を工夫することで、学習の効率が大きく変わります。
ただ黒板を写すだけではなく、目的を意識しながら、自分専用の参考書を作る気持ちで、自分にとって分かりやすいノートを作ることを心掛けましょう。
学習のサポートツールとしてノートを最大限に活用し、効率よく知識を身につけていきましょう。
家庭教師のマスターでは、小中学生に向けたノート作りからサポートしています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【小学生コース】について
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!























