効率的な古文単語の覚え方と勉強法|古文が嫌いな中高生必見!
公開日:2025年3月24日

「英単語と比べて、古文の単語は覚えにくい…」と感じる中高生は多いのではないでしょうか?
このコラムでは、古文単語の効率的な覚え方や勉強法を詳しく解説します!また、覚える単語数の目安やオススメの古典作品もご紹介します。古文が苦手な人は必見の内容です!
古文単語はどれくらい覚えるべき?
古文単語を覚えようと思っても、「どれくらい覚えればいいの?」と疑問に思う人は多いはず。英単語と違って、膨大な数を暗記する必要はありません。受験レベルごとの目安を確認して、効率よく学習しましょう!
1. 基本単語を厳選する
高校受験レベルの目安
高校入試では、古文の出題範囲は限られており、基本的な単語を押さえておけば十分です。目安としては、100語程度を覚えておくと安心でしょう。
「あはれ(しみじみとした情趣)」「いと(とても)」などの基本的な意味を押さえれば、内容の理解が可能です。
大学受験レベルの目安
大学受験では、より多くの古文単語を覚える必要があります。共通テストレベルでは300〜400語、難関私大・国公立二次試験レベルでは600語程度が目安です。
ただし、600語すべてを暗記するのではなく、基本単語を確実に定着させることが最優先です。
2. 単語帳は1冊で十分!
「単語帳をいくつも買って、結局どれも中途半端…」そんな経験はありませんか? 実は、古文単語帳は1冊に絞るのがベストです。
たくさんの単語帳に手を出すよりも、1冊を繰り返し復習する方が記憶の定着が早くなります。どの単語帳を使うか迷ったら、学校で指定されたものや定評のある1冊 を選びましょう。
さらに、単語帳の使い方も大切です。
・1周目は、ざっと意味を確認するだけでOK
・2周目以降で、よく出る単語を重点的に覚える
・例文や文章の中で意味を確認しながら覚える
「1回読んだだけでは覚えられない…」と焦らず、何度も繰り返すことが記憶のカギになります。
3. 古文単語の特徴
古文単語は英単語とは違った特徴を持っています。その特徴を知ることで、暗記の負担を減らすことができます!
派生語が少ない(英語と比較)
英単語は「act(行動する)」→「active(活動的な)」→「action(行動)」のように派生語が多いですが、古文単語は派生語がほとんどありません。 そのため、古文単語は一つひとつ暗記する必要がありますが、逆に考えると、「1つの単語を覚えたら、それ以上覚える関連語が少ない」 というメリットもあります。
例えば、「あはれ」という単語は単体で使われることが多く、「あはれなり」と活用する程度です。こうしたシンプルさを活かして、確実に1語ずつ覚えていきましょう。
派生語が少ない(英語と比較)
英単語は1つの単語に対して意味が比較的限定されていることが多いですが、古文単語は1つの単語に複数の意味があるのが特徴です。
例えば、
・「わたる」→「行く・通る」「一面に〜する」「生きる」
・「しのぶ」→「我慢する」「人目を避ける」「恋しく思う」
このように、文脈によって意味が変わる ため、単語単体で覚えるのではなく、例文とセットで覚えることが重要です。
※「しのぶ」は『恋ひしのぶ』なら「恋しく思う」、『人目をしのぶ』なら「人目を避ける」 というように、使い方で判断する練習をしましょう!

効率的な古文単語の覚え方・勉強法8選
古文単語を効率よく覚えるためには、やみくもに暗記するのではなく、工夫を取り入れることが大切です。ここでは、効果的な古文単語の覚え方を8つのポイントに分けて解説します。
1. 基本単語を厳選する
古文単語を覚える際は、最初からすべてを暗記しようとするのではなく、頻出の基本単語を優先的に覚えることが重要です。
特に高校受験や大学受験では、よく出題される単語が決まっているため、まずはそのリストを作成し、計画的に学習を進めましょう。
| 高校受験レベル | 100語程度 |
|---|---|
| 共通テストレベル | 300〜400語程度 |
| 難関大学受験レベル | 600語程度 |
これらの単語を効率よく覚えることで、古文読解の理解度が飛躍的に向上します。
2. イメージで覚える
古文単語の多くは、現代の言葉とは異なる感覚を持つため、単なる意味の丸暗記ではなく、情景や感情をイメージしながら覚えることが効果的です。
例えば、
・「あはれ」 → 夕焼けを見てしみじみとした気持ちになるようなイメージを持つと理解しやすくなります。
・「こころにくし」 → 品があって奥ゆかしい人を思い浮かべると、単なる意味の暗記よりも記憶に残りやすくなります。
言葉の背景を想像しながら学習することで、単語のニュアンスを直感的に理解できるようになります。
3. 現代語とのつながりで覚える
古文単語には、現代語と共通する要素を持つものも多くあります。そのつながりを意識すると、よりスムーズに覚えられます。
例えば、
・「あいなし」 → 「愛がない=つまらない」と考えると意味を連想しやすい
・「うつくし」 → 「美しい」の語源と関連付けると理解しやすい
・「いたし」 → 「痛い」とつながるため、「ひどい」「とても」といった意味が直感的に理解しやすくなる
この様に、現代語と関連づけながら学習することで、単語をよりスムーズに覚えられることがあります。
4. 例文とセットで覚える
古文単語を暗記するだけでは、文章の中で意味を正しく理解できないことがあります。そのため、例文と一緒に覚えることが大切です。
例えば、
・「あはれ」 → 「花の色があはれなり(しみじみとした美しさがある)」のように、具体的な文の中で使われる場面を意識すると、単語のニュアンスが自然と身につきます。
・「おぼつかなし」 →「おぼつかなくて夜も眠れない(気がかりで落ち着かない)」といった文で覚えると、実際の古文読解の際に意味を推測しやすくなります。
単語を単体で覚えるのではなく、例文を通して覚えることで、実践的な力を身につけることができます。
5. 書いて覚える
古文単語を記憶するためには、視覚だけでなく、実際に手を動かして書くことも有効です。
単語を何度も書き出すことで、記憶が定着しやすくなります。
ただし、ひたすら書き続けるのではなく、意味を考えながら書くことが重要です。
例えば、
・1日10語程度を3回ずつ書き、その都度意味を口に出すと、より効率的に学習できます。
・関連語や類義語をセットで書き出すと、意味の幅が広がり、より確実に記憶に残ります。
6. 音読やリズムで覚える
古文単語を覚えるときは、音読を活用することで、視覚だけでなく聴覚も使って記憶に定着させることができます。
声に出して読むことで、単語の響きやリズムが印象に残りやすくなり、長期間忘れにくくなります。
また、リズムに乗せて覚える方法も効果的です。「あはれ、いと、をかし、めでたし」といった単語をリズムよく発音することで、単調な暗記作業が楽しくなり、記憶にも定着しやすくなります。
7. 単語帳を使って覚える
古文単語を効率よく覚えるためには、単語帳を活用するのが効果的です。
特に、一冊の単語帳を繰り返し使うことが重要で、何度も目にすることで記憶が定着しやすくなります。また、書く・読むを繰り返しながら学習することで、より深く理解できるようになります。
さらに、スマホアプリやフラッシュカードを活用すると、スキマ時間にも手軽に復習できるため、効率的な学習が可能になります。単語帳を上手に活用し、繰り返し学習することが大切です。
8. 古文の文章で実践的に覚える
古文単語を覚えるだけではなく、実際の古文の文章の中で確認することで、より実践的な知識として定着させることができます。
文章の中で単語がどのように使われているのかを意識しながら読むと、文脈から意味を推測する力も養われます。また、「枕草子」や「徒然草」のような比較的読みやすい古典作品を活用すると、頻出単語が自然に身につきます。知らない単語が出てきた場合も、すぐに意味を調べるのではなく、文脈から推測する練習をすることで、読解力が向上します。

レベル別おススメ古典
古文の読解力を向上させるためには、自分のレベルに合った作品を選ぶことが大切です。初心者から上級者まで、それぞれのレベルに応じた古典を読むことで、無理なく古文に親しむことができます。ここでは、レベル別におすすめの古典作品を紹介します。
1. 初心者向け(文法や語彙に慣れたい人向け)
古文にまだあまり慣れていない人や、文法や語彙の基礎を固めたい人には、比較的平易な表現で書かれている作品を読むのがおすすめです。
物語の展開が分かりやすく、短い話が多い作品を選ぶと、古文の文章に親しみやすくなります。
『竹取物語』
『竹取物語』は、日本最古の物語とされる作品で、かぐや姫の誕生から昇天までの話が描かれています。平易な表現が多く、物語の内容も親しみやすいため、初めて古文を読む人に最適です。
『伊勢物語』
『伊勢物語』は、平安時代の歌物語で、主人公の男の恋愛や旅のエピソードが中心になっています。一つ一つの話が短いため、少しずつ読み進めることができ、古文に慣れるのに適した作品です。
『徒然草』
『徒然草』は、鎌倉時代の随筆で、吉田兼好が日常の出来事や人生観について綴ったものです。短い話が多く、現代でも共感できる内容が多いため、古文のリズムに慣れながら読解力を養うことができます。
2. 中級者向け(古文のリズムに慣れたい人向け)
ある程度古文に慣れ、リズムを意識しながら読めるようになりたい人には、平安時代の随筆や物語、また軍記物語などを読むのがおすすめです。
これらの作品は美しい表現が多く、古文特有の言い回しを自然に身につけることができます。
『枕草子』
『枕草子』は、清少納言が宮廷生活の様子や四季の移り変わりについて記した随筆です。
「春はあけぼの」といった有名な一節も含まれ、古文の美しさを味わうことができます。リズムのよい文章が多く、音読しながら読むことで、古文の流れをつかむ練習にもなります。
『平家物語』
『平家物語』は、平安時代末期の武士の栄枯盛衰を描いた軍記物語で、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」という冒頭が特に有名です。韻を踏んだ美しい文章が特徴で、声に出して読むと古文の独特のリズムが身につきます。
『源氏物語』
『源氏物語』は、日本文学の最高峰ともいわれる長編物語で、貴族社会の恋愛や人間関係が描かれています。内容はやや難解ですが、情景描写や登場人物の心理表現が豊かで、古文の魅力を深く味わうことができます。
3. 上級者向け(深い読解力を身につけたい人向け)
古文に十分慣れ、より高度な読解力を養いたい人には、哲学的な要素を含む随筆や歴史書、さらには江戸時代の怪談文学などを読むのがおすすめです。
これらの作品は、言葉の使い方や表現が複雑で、深く読み込む力が求められます。
『方丈記』
『方丈記』は、鴨長明による随筆で、無常観や人生観が描かれています。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という一節が有名で、平易な表現ながらも深い思想を読み取る力が求められます。
『大鏡』
『大鏡』は、平安時代の歴史物語で、藤原道長を中心とした貴族社会の権力争いが描かれています。登場人物が多く、複雑な人間関係を理解しながら読む必要があるため、上級者向けの作品といえます。
『雨月物語』
『雨月物語』は、江戸時代に書かれた怪談集で、美しい古文表現と幻想的な内容が特徴です。話の展開が複雑で、細かい表現の違いを読み取る力が求められるため、深い読解力を身につけるのに最適な作品です。
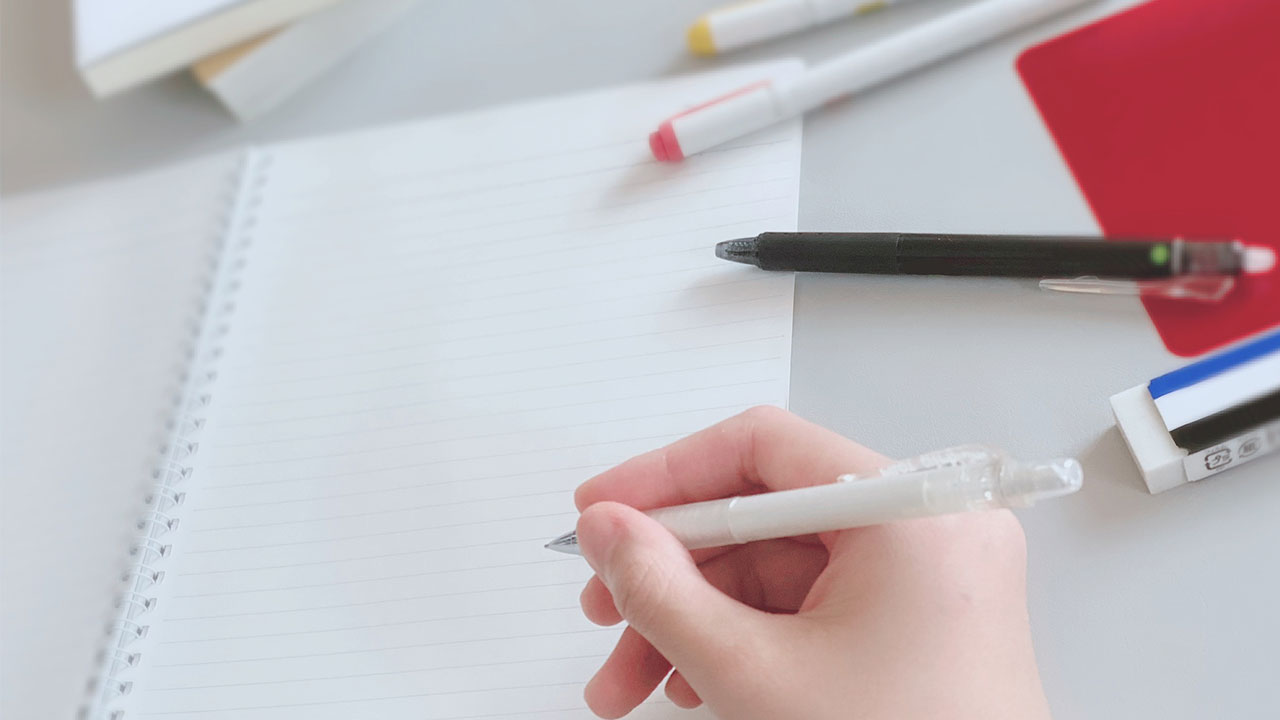
まとめ
今回は「古文単語の覚え方」をテーマに書いてきました。
古文単語の暗記や読解は、一見すると難しく感じるかもしれません。しかし、効率的な学習法を取り入れ、自分のレベルに合った学習を進めることで、確実に理解を深めることができます。
古文の学習は、単なる暗記作業ではなく、言葉の美しさや歴史的背景を楽しむことができるものでもあります。効率的な方法を活用しながら、自分のペースで学習を進め、古文の魅力を深く味わいましょう。
家庭教師のマスターでは、古文が苦手な生徒さんに向けたサポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
⇒【高校生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























