理科が苦手な中学生へ!効率的な勉強法と克服のコツを解説
公開日:2025年4月17日

このコラムでは、苦手とする人が意外と多い理科の勉強法について解説していきます!理科が苦手になる理由、苦手になりやすい単元、分野別の勉強法、定期試験対策や受験対策まで徹底解説します!理科を苦手にしている中学生の方は、ぜひ参考にしてください!
理科の勉強が苦手になる要因は?
理科を苦手としている中学生は少なくありません。実は、理科が苦手になる理由にはいくつか共通点があります。
まずは、なぜ理科が苦手に感じてしまうのか、その要因をしっかり理解することが、克服の第一歩です。ここでは、よくある4つの原因を解説します。
1. 用語や公式が多くて覚えきれない
理科には専門的な言葉や覚えるべき公式がたくさん出てきます。
例えば「光合成」や「電圧」「密度」など、普段の生活ではあまり使わない用語が多いため、なかなか覚えられずに苦手意識を持つことがあります。
さらに、物理や化学では「密度=質量÷体積」などの難しい公式が出てきて、「どうしてこの式になるのか?」という意味を理解しないまま丸暗記しようとすると、テストで応用問題が出た時に対応できなくなってしまいます。
2. 計算問題が難しく感じる
中学以降の理科では、計算問題の比率が増えていきます。
電流や力の問題、化学反応の質量計算など、算数や数学の知識と理科の知識を組み合わせて考えなければならない問題が多くなります。
例えば、「オームの法則(電圧=電流×抵抗)」では、単位の扱いや計算ミスが原因でつまずくこともよくあります。また、問題文を読み取って「どの公式を使うのか?」を判断するのが難しいケースもあります。
計算問題に慣れていないと、「理科=難しい」と思ってしまい、苦手意識につながるのです。
3. 実験や観察の意図が分からない
中学理科では、実験や観察の問題がよく出題されます。
しかし、「なぜその実験をするのか?」「この実験で何を確かめたいのか?」といった意図を理解していないと、ただ作業として流してしまい、結果も印象に残りません。
例えば、「植物に光を当てないと光合成はどうなるか?」という実験をした時、実験の目的を理解していないと、「なんとなく葉っぱの色が変わった」という表面的なことしか覚えられません。
実験の「理由」と「結果」のつながりを意識できないままにしておくと、理科の理解が深まらず、どんどん苦手になってしまいます。
4. 興味が持てず、理科の勉強自体が後回しになる
「そもそも理科の内容に興味を持てない…」となると、「なんとなく苦手」と感じやすくなります。
理科が好きな人は、自然現象や宇宙の話、生き物の仕組みにワクワクしながら勉強できますが、興味がわかない人にとっては、どの単元も「覚えるだけでつまらない」と感じてしまうことが多いです。
その結果、理科の勉強が後回しになり、テスト前に焦って詰め込み学習をすることになります。理解が追いつかないまま学年が進むと、ますます理科に苦手意識を持ってしまうという悪循環に陥ってしまうのです。
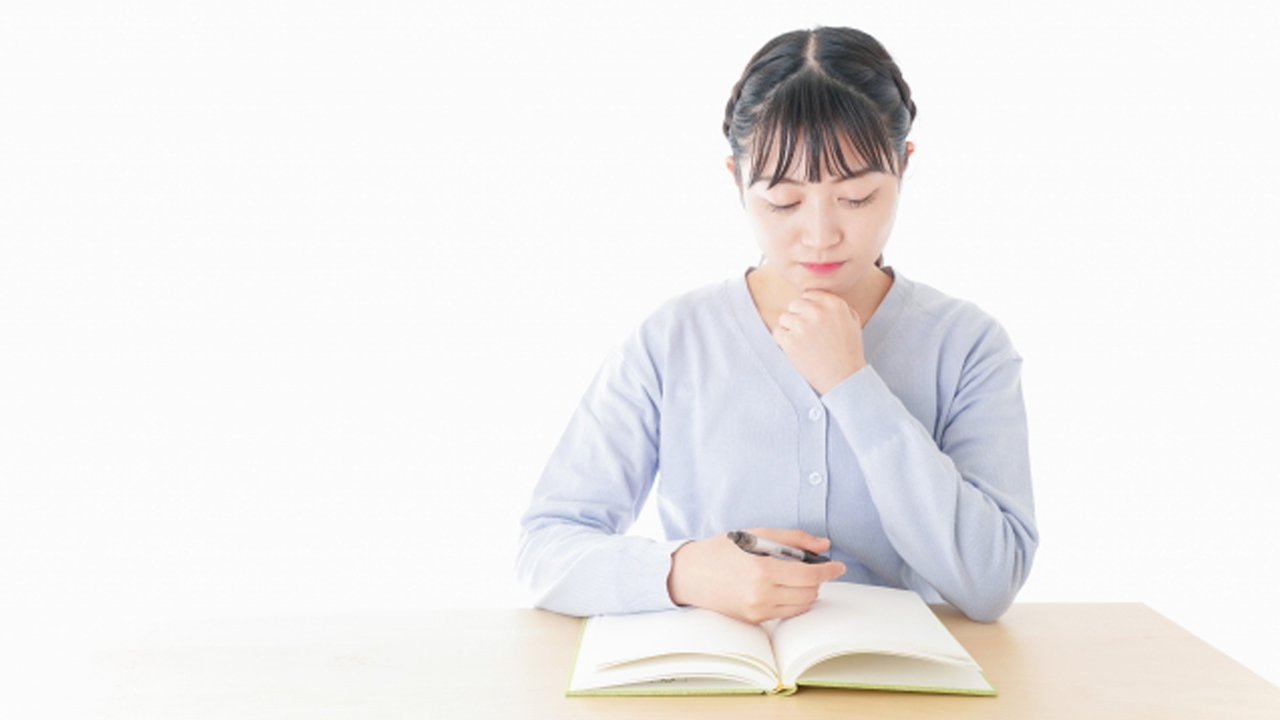
苦手になりやすい単元は?|分野別に解説!
理科の中でも、「この分野がどうしても苦手…」という声は多く聞かれます。
理科は物理・化学・生物・地学の4分野に分かれており、それぞれに特徴やつまずきやすいポイントがあります。
ここでは、分野ごとに特に苦手になりやすい単元を取り上げ、なぜ難しく感じるのかを解説します。自分がどこで苦手意識を持っているのかを見つける参考にしてみてください。
1. 物理
力のつり合いと作用・反作用
物理の中でも「力のつり合い」や「作用・反作用」は、目に見えない力をイメージで理解しなければならないため、苦手に感じる生徒が多い単元です。
「力がつり合っている状態ってどういうこと?」「押してるのに反対にも同じ力が働くの?」など、抽象的な内容を理解しなければいけないことが多く、現実の動きと結びつけるのが難しく感じる人が多いです。
図や矢印を使った学習がカギになります。
電流と回路
「電圧=電流×抵抗」のような公式を使うオームの法則や、直列・並列回路の違いもつまずきやすいポイントです。
電流の向きや分かれ方、電圧の分配など、細かいルールを覚えるだけでなく、回路図を見て判断する力も必要になります。
どの回路にどの法則が当てはまるのかを整理して覚えることが重要です。
2. 化学
化学変化と質量保存の法則
化学変化では、物質が変化する時の質量が変わらないことを学びますが、それをもとにした計算問題が苦手という人は多いです。
「反応前の物質の質量から、反応後の物質の量を求める」といった問題は、算数や数学の力も必要になってきますが、意味が分からないまま数字だけを追っていると、余計に混乱しやすい単元です。
物質の状態変化
水が蒸発したり氷になるような状態変化は身近ですが、それを理科の知識として説明されると一気に難しく感じることがあります。
「分子がどう動くのか」「エネルギーがどう関係するのか」など、目に見えない世界の話をイメージする必要があるため、なかなか理解が進まないことも多いです。
3. 生物
光合成と呼吸
光合成や呼吸のしくみは、「二酸化炭素+水 → 酸素+栄養分」のような化学反応式を伴って説明されます。これらをただ暗記するだけでは、なぜその反応が起こるのか理解できず、応用問題になると対応できなくなってしまいます。
また、呼吸と光合成の違いや関係を混同することも多く、混乱の原因になります。
消化と吸収
食べ物が体の中でどう分解され、吸収されるかを学ぶこの単元では、「アミラーゼ」「ペプシン」などの消化酵素の名前や、それぞれがどこで働くのかを細かく覚える必要があります。
また、口・胃・小腸など器官の役割も整理しないとごちゃごちゃになりがちで、「全部同じに見える…」と感じてしまう人も少なくありません。
4. 地学
天気の変化と気圧配置
天気に関する単元では、天気図を読み取る力が必要になります。
高気圧・低気圧の位置や風の向き、前線の種類などを見ながら、どんな天気になるのかを予測しなければなりません。
情報量が多く、図を見て判断する問題が中心なので、苦手意識を持つ人が多い単元です。
地層の成り立ち
地層や岩石の種類、化石の名前や特徴など、覚えることが多いのがこの単元の特徴です。
見た目や性質の違いをセットで覚える必要があるため、単なる暗記では対応しきれない場面も出てきます。
また、地層の重なりから地球の歴史を読み取る問題では、時間の流れをイメージする力も求められるため、ややハードルが高いと感じる人も多いです。
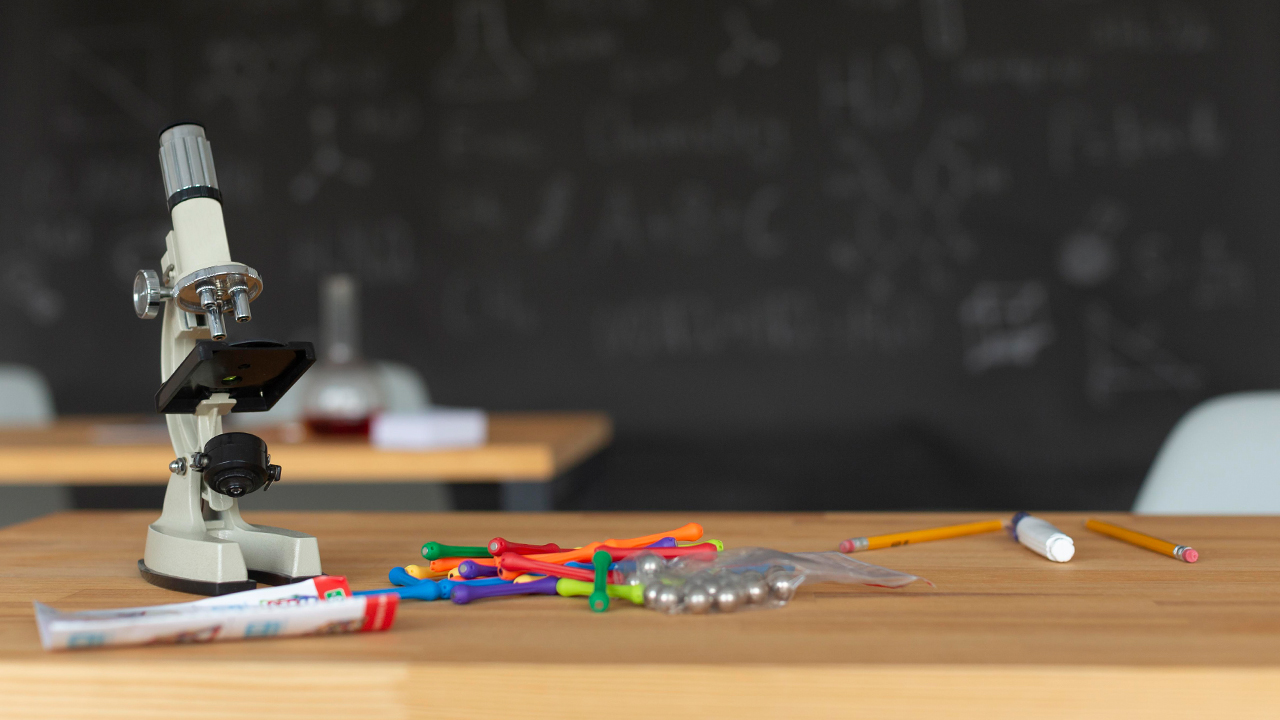
理科の効率的な勉強法は?|分野別に解説!
理科を効率よく勉強するためには、分野ごとに異なる「理解のコツ」があります。理科は暗記だけでなく、仕組みや流れ、考え方を理解することがとても大切です。
ここでは、物理・化学・生物・地学の4分野ごとに、苦手を克服しやすくなる効果的な勉強法を紹介します。自分が苦手とする分野に合わせて、ぜひ実践してみてください。
1. 物理|公式と図解を組み合わせて理解力アップ
物理では、公式をただ丸暗記するのではなく、「どういう意味なのか?」を理解することが大切です。例えば「力のつり合い」や「オームの法則」などは、図を使って視覚的に覚えると理解しやすくなります。
オススメの勉強法は、問題を解くときに必ず力の向きや回路の流れを自分で図に描いてみることです。矢印を使って力の関係を視覚化することで、イメージがしやすくなります。
また、公式を丸暗記するのではなく、「どうしてこの式になるのか」という理由や例題を通して理解することも重要です。身近な現象と結びつけて考えると、ぐっと分かりやすくなります。
2. 化学|「なぜそうなるか」を押さえた暗記がカギ
化学では、暗記が必要な部分が多くありますが、丸暗記ではなく理由とセットで覚えることがポイントです。
例えば、化学変化で「銅+酸素→酸化銅」という反応があるとき、「なぜ酸素が必要なのか?」「どんな変化が起きているのか?」を理解しておくと記憶に残りやすくなります。
また、「質量保存の法則」のような計算問題では、単位(g、cm³など)を正確に扱う練習をしておくことも重要です。
反応前と後で何がどう変化しているのかなどを、図や表を使って視覚的に整理すると、理解が深まります。
3. 生物|フローチャートや図でつながりを理解
生物の分野では、フローチャートやイラストで整理する勉強法が効果的です。
例えば「消化の流れ」や「光合成と呼吸の関係」は、文章だけでは覚えにくいですが、図や流れ図でつなげて覚えることで、理解と記憶の両方がしやすくなります。
また、「暗記だけでは太刀打ちできない」と感じる時こそ、用語と働きをセットにして覚えることを意識しましょう。
体のしくみや植物の働きは、具体的なイメージを持つことが理解への近道です。
4. 地学|天気図や地層の問題は「パターン練習」が有効
地学では、天気図や地層のような読み取り問題に慣れることが大切です。
パッと見てわからなくても、よく出るパターンを繰り返し練習することで、判断力がついてきます。
例えば、天気図の「高気圧の周りを時計回りに風が吹く」「寒冷前線が通ると天気が急に変わる」といった基本ルールを理解し、それを元に複数の類似問題にチャレンジすることで正答率が上がっていきます。
また、地層や化石の問題も、出題されやすいパターンを中心に演習することで、見慣れた問題として解けるようになります。
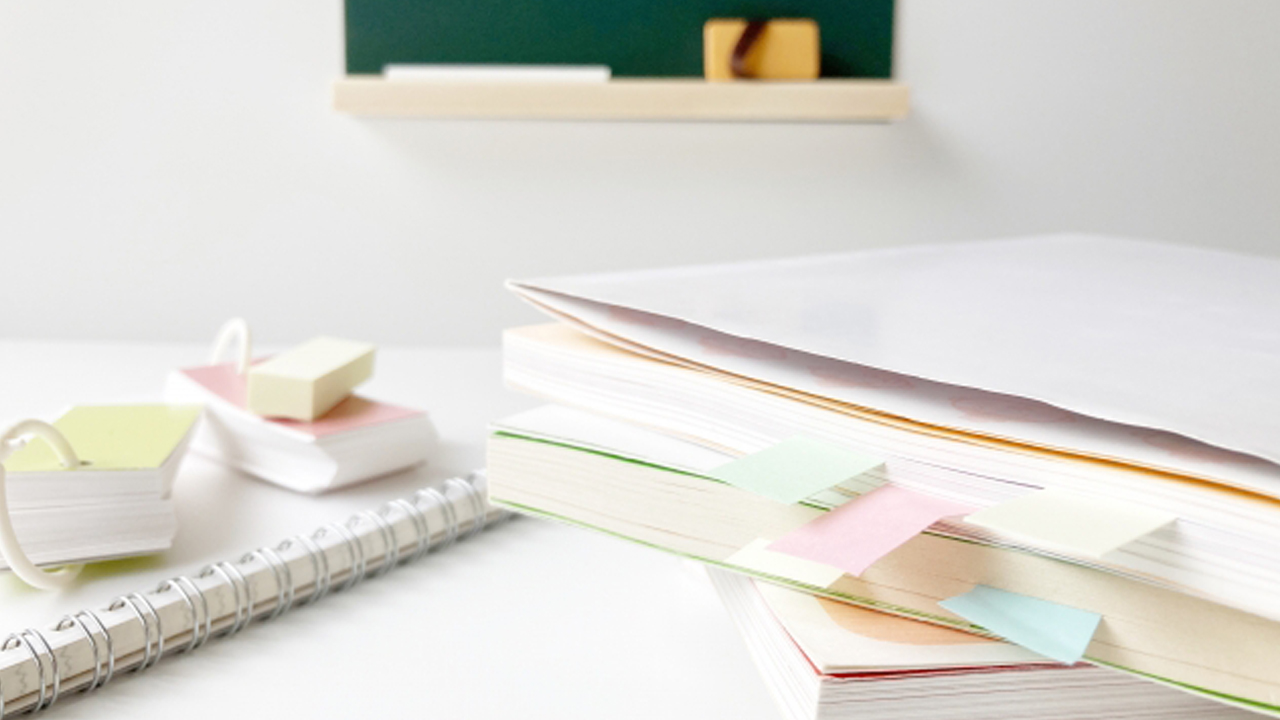
理科の効率的な勉強法は?|目的別に解説!
理科の勉強をする時、目的によって勉強のやり方を変えることがとても大切です。
定期テストでは「学校の授業内容」をしっかり理解して得点することが求められますが、高校受験では「総合的な応用力」や「複数分野を横断した理解力」が問われます。
ここでは、目的別に理科を効率よく勉強する方法を紹介します。今の自分の目標に合わせて、適した勉強法を選んでいきましょう。
1. 定期テストの対策
定期テストで大切なのは、授業で習った内容を正確に理解し、問題として解けるようにすることですので、次のようなポイントを意識しましょう。
教科書・ノートをしっかり復習する
テスト範囲の中心は学校の授業です。まずは教科書や授業ノートを見返して、「先生が強調していたポイント」や「実験内容」「図や表」などを再確認しましょう。
太字の語句や公式は確実に覚える必要があります。
成績が上がるノートの取り方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「成績が上がるノートの取り方|上手なノートづくりのポイントとは?」
学校のワークやプリントを繰り返し解く
授業で使った問題集やプリントは、テストにそのまま出ることも多いです。
1回解いて終わりにせず、間違えた問題は印をつけて何度も解き直すのが効果的です。
語句だけでなく“仕組み”も理解する
例えば「光合成=二酸化炭素+水 → 酸素+養分」と覚えるだけでなく、なぜこの反応が起きるのか、どこで行われるのかも理解しておくと、記述問題にも対応できます。
暗記は短時間×毎日がおすすめ
用語の暗記は一夜漬けよりも、毎日少しずつ覚える方が効果的です。
夜の10分、朝の10分など、こまめな復習の習慣化が得点アップのカギです。
効率的な暗記の方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効率的な暗記の方法とは?|苦手な暗記を克服するオススメ8つの方法」
2. 高校受験対策
高校受験では、中1〜中3までの全範囲から出題されるため、広い範囲の知識と応用力が必要になります。次のような勉強法が有効です。
教科書レベルの内容を一通り復習する
苦手な分野を中心に、中1・中2の内容も振り返ることが重要です。
特に物理や化学は積み重ねが大切なので、基本的な公式や考え方を見直しましょう。
過去問や予想問題で実戦力をつける
入試では、初見の問題や複数分野が組み合わさった問題も出ます。公立高校の過去問や模試形式の問題集を使って、入試レベルの出題に慣れておくことが大切です。
図・グラフ・表を読み取る力を鍛える
入試問題では、「図や表を見て考える」タイプの問題がよく出題されます。
情報を素早く読み取り、自分の知識と結びつけて答える練習を重ねましょう。
間違えた問題は「なぜ間違えたか」を分析する
ただ解き直すだけでなく、「どうしてその選択肢を選んだのか」「どこで考え違いをしたのか」を書き出してみましょう。
解けるようになるまで復習する習慣が、合格につながります。

まとめ
理科が苦手になる原因は人それぞれですが、つまずきやすいポイントを知り、自分に合った勉強法を取り入れることで、少しずつ克服することができます。
分野ごとの理解のコツや、目的に応じた対策を意識して取り組めば、理科は決して難しい教科ではありません。
大切なのは、あきらめずにコツコツ続けること。今日からできることから始めて、理科を得意科目に変えていきましょう。
家庭教師のマスターでは、理科が苦手な中学生に対する学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























