中学の入学準備でやるべきこと|新中学生と保護者の方必見!
公開日:2025年3月11日

これから中学に入学する新入生の方と保護者の方向けに、中学の入学準備でやるべきことを詳しく解説します。また、中学入学前に親子で話し合うべきこと、入学手続き、学習面の準備、持ち物の準備についても詳しくご紹介します。準備をしっかり済ませて新しい生活をスタートしましょう!
中学入学前に、親子で話し合っておくべきこと
お子さんが中学生活をスタートするにあたり、どんな準備をしておくべきか悩むご家庭も多いでしょう。
勉強や部活動、スマホの使い方など、事前に親子でしっかりと話し合うことで、中学生活をより充実したものにすることができます。ここでは、特に大切な七つのポイントについて詳しく解説します。
1. 塾や家庭教師を利用するか?
中学では、定期テストや成績が高校受験に直結するため、勉強の仕方が重要になります。
小学校のときと同じように授業を受けるだけでは、テストで良い点が取れないこともあるため、塾や家庭教師を利用するかどうかを考えておくことが大切です。
塾を利用する場合、集団指導と個別指導のどちらが適しているのかを検討する必要があります。
集団塾はライバルと切磋琢磨しながら学べる環境があり、個別指導塾では苦手科目を重点的に学ぶことができます。
家庭教師を選択する場合は、一対一の指導で自分のペースに合わせて学習できるため、部活動や習い事と両立しやすいというメリットがあります。塾や家庭教師を利用しない場合でも、通信教材や学習アプリを活用して自主学習のサポートをする方法もあります。
どの方法が最適かは、お子さんの学習スタイルや目標によって異なります。成績向上や高校受験を意識しながら、無理のない学習環境を整えていきましょう。
塾と家庭教師についてもっと知りたい方はこちら
⇒「塾と家庭教師どっちがいいの?|どちらが子供に合うか徹底検証!」
2. 習い事を続けるか?
小学校で続けていた習い事を中学でも継続するかどうかを決めることも重要です。
中学では勉強の負担が増えるだけでなく、部活動が始まるため、時間の使い方を考える必要があります。
習い事を続ける場合は、部活動との両立が可能かどうかを確認しなければなりません。また、帰宅時間が遅くなることで勉強時間が確保できなくなる可能性もあるため、習い事を継続する場合はスケジュールを調整しながら無理のない範囲で続けることが大切です。
逆に、習い事をやめる場合は、本人が本当に納得しているかどうかを確認することが重要です。
受験勉強を優先するために辞めるケースもありますが、本人が続けたいと感じている場合は、無理に辞めさせるのではなく、別の方法で続けられる方法を考えることも一つの選択肢となります。
習い事は学業と同じように、お子さんの成長に大きな影響を与えます。親子でしっかり話し合い、本人の気持ちを尊重しながら決めていきましょう。
3. スマホの使用ルールを決める
中学に入ると、スマホを持つかどうか、また使用ルールをどうするかが大きな問題になります。
スマホを持つことで、塾や部活動の連絡が取りやすくなり、友達とのコミュニケーション手段としても便利というメリットがありますが、一方で、SNSやゲームの使用によって勉強の時間が減ってしまう可能性もあります。
スマホを持つ場合は、使用時間や利用目的について事前にルールを決めておくことが重要です。
特に、夜遅くまでスマホを使うことによって生活リズムが乱れないように、寝る前にはスマホをリビングで充電するなどのルールを決めると良いでしょう。
また、SNSの利用に関しても、トラブルに巻き込まれないように、投稿する内容や個人情報の管理についても話し合っておく必要があります。
スマホは便利なツールですが、正しく使わなければ生活に悪影響を及ぼすこともあります。事前にしっかりとルールを決めて、中学生活を快適に送れるようにしましょう。
ゲーム・ネット依存の子どもへの対策についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ゲーム・ネット依存の子どもへの家族の接し方|セルフチェックリスト付き」
4. お小遣いのルールを決める
中学生になると、お小遣いの使い道が広がるため、親子でルールを決めておくことが大切です。
「毎月決まった金額を渡す」か「必要なときに渡す」のか、「どのような使い道が許されるのか」について話し合いましょう。
お小遣いを管理する習慣を身につけることで、計画的にお金を使う力が養われます。
お小遣い帳をつける習慣をつけると、自分のお金の使い方を把握しやすくなり、無駄遣いを防ぐことができます。
お金の価値を理解しながら、責任を持って管理できるように話し合いをしておきましょう。
5. 部活動について
部活動は中学生活の大きな要素の一つです。どの部活に入るのか、また勉強との両立が可能かを事前に話し合っておくことが大切です。
運動部にするのか文化部にするのか、活動時間はどのくらいなのか、顧問の先生や先輩の雰囲気はどうなのかを事前に確認しておくと、入部後のギャップを防ぐことができます。
部活動を続けることで、仲間との絆が深まり、協調性や忍耐力を養うことができますが、練習時間が長すぎると勉強に影響が出る可能性もあります。無理のない選択をすることが重要です。
6. 通学方法を確認する
中学では通学距離が長くなることが多いため、安全な通学ルートを確認しておくことが重要です。
徒歩や自転車通学の場合は、交通ルールを守ることが大切です。電車やバスを利用する場合は、定期券の購入や乗り換えの練習を事前にしておきましょう。
7. 交友関係・いじめ対策
中学では新しい友達ができる一方で、いじめやトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
友人関係の悩みを一人で抱え込まないように、困ったときは親や先生に相談できる環境を作っておきましょう。SNSを通じたトラブルにも注意し、ネット上での発言には責任が伴うことを理解しておくことが大切です。
中学生のいじめから身を守る為にもっと知りたい方はこちら
⇒ 「中学生のいじめへの解決法とサポート|いじめから身を守る為には」

中学入学準備【入学手続き、入学説明会】
中学校への進学に向けて、入学手続きや説明会への参加は欠かせません。進学先によって手続きの流れや準備するものが異なるため、早めに確認し、スムーズに進めることが大切です。
ここでは、地元の公立中学、学区外の公立中学、私立中学に進学する場合の手続きについて詳しく解説します。
1. 地元の公立中学に進学する場合
地元の公立中学に進学する場合、基本的な手続きは比較的シンプルです。
通常、入学の数か月前に自治体から「入学通知書」が送られます。この通知には、お子さんが進学する中学校の名前や、入学に関する手続きの案内が記載されています。通知が届いたら、学校や教育委員会の指示に従い、必要な準備を進めていきましょう。
入学説明会は、入学予定の中学校で開催されることがほとんどです。
入学説明会では、学校の生活ルールや学用品の準備について詳しく説明されます。制服や体操服、指定の学用品の購入方法についても案内があるため、必要なものをメモしておくとスムーズです。
また、通学方法や学校のルールについても詳しく説明されるため、疑問点があればこの機会に確認しておくと良いでしょう。
健康診断や予防接種の確認も重要です。自治体によっては、小学校卒業前に健康診断を受けることが義務付けられている場合があります。未接種の予防接種がある場合は、早めに受けておくと安心です。
2. 越境して学区外の公立中学に進学する場合
学区外の公立中学に進学する(越境入学)場合、通常の入学手続きに加えて、教育委員会への申請が必要になります。住んでいる自治体によって、越境入学が認められる条件が異なるため、早めに情報を確認しておきましょう。
越境入学を希望する場合、まず市区町村の教育委員会に「指定校変更申請書」を提出する必要があります。
申請理由として、越境入学をする理由(親の転勤、引っ越し予定、病気、いじめなど)が求められる場合が多いです。教育委員会の審査を通過すると、正式に学区外の学校への入学が認められます。
越境入学が認められた場合でも、入学説明会には必ず参加しましょう。学校のルールや持ち物についての案内を受けることで、入学後の準備がスムーズになります。
また、学区外の学校に通う場合、通学距離が長くなることがあるため、通学ルートの確認や定期券の購入手続きも事前に済ませておくと良いでしょう。
越境入学には、自治体ごとのルールがあるため、必ず事前に教育委員会や希望する中学校へ問い合わせをし、手続きのスケジュールを把握しておくことが大切です。
3. 私立中学に進学する場合
私立中学に進学する場合、公立中学とは異なり、受験が必要になります。
合格後は、指定された期日までに入学手続きを済ませる必要があるため、スケジュールをしっかり管理することが大切です。
私立中学の入試は、多くの場合1月から2月にかけて行われます。合格発表後、入学金や授業料の一部を期日までに支払うことで、正式に入学が決定します。
手続きの締切が短い場合が多いため、支払いの期日を事前に確認しておきましょう。
入学説明会は、合格者向けに実施されます。私立中学は学校ごとに独自のルールや教育方針があるため、説明会に参加して学校生活の詳細を把握することが重要です。
制服や体操服、教科書の購入手続きについても説明があるため、必要なものを確認し、早めに準備を進めておくと良いでしょう。
また、私立中学では入学前に健康診断を受けることが義務付けられている場合があります。
入学前のオリエンテーションやプレ授業を実施する学校もあるため、スケジュールを確認し、必要な準備を整えておきましょう。
通学方法の確認も重要です。特に電車やバスを利用する場合、定期券の購入手続きを事前に済ませておくと安心です。私立中学は通学範囲が広いため、実際に登校ルートを試しておくと、入学後の不安が軽減されます。
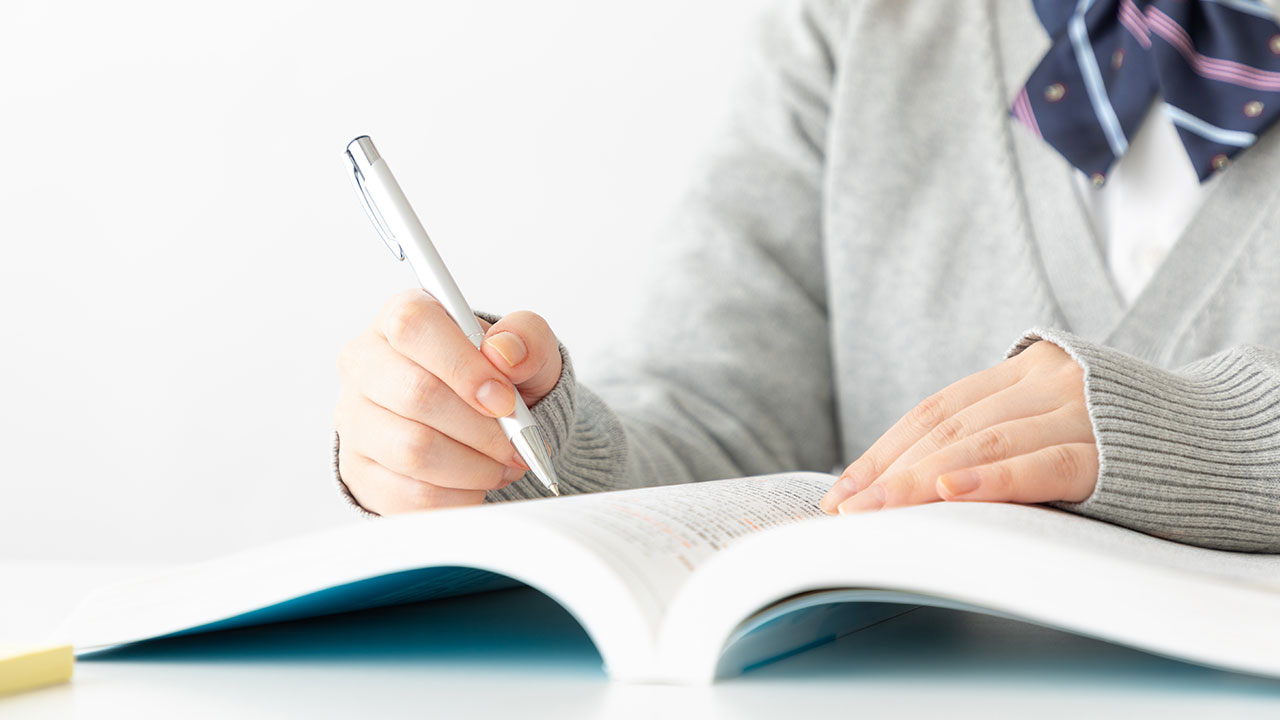
中学入学準備【学習面の準備】
中学入学に向けて、学習面の準備をしっかり整えておくことが大切です。
中学では授業の進み方が速くなり、定期テストの成績が高校受験にも関わってくるため、小学校の復習をしながら、中学の予習も進めておくと安心です。また、自宅学習の習慣を作ることで、中学の勉強にスムーズに対応できるようになります。
ここでは、学習面で準備しておきたいポイントについて詳しく解説します。
1. 小学校の復習をしよう
中学の勉強は小学校で学んだ内容が基礎となるため、特に重要な単元を中心に復習しておくことが大切です。苦手な分野をしっかり克服し、スムーズに中学の授業に取り組めるようにしておきましょう。
算数
算数は中学で「数学」へと変わり、より計算の精度やスピードが求められるようになります。
小数や分数の計算はもちろん、割合や速さ、比の計算がしっかりできるかを確認しておきましょう。
また、図形の面積や体積の求め方も復習しておくと、中学の幾何の学習にスムーズに入ることができます。中学の数学では負の数や文字式を扱うため、簡単な代数的な考え方にも慣れておくと良いでしょう。
国語
中学の国語では、文章の読解力がより重要になります。説明文や物語文を読んで、内容をしっかり理解する力をつけておきましょう。
また、小学校で習った漢字を復習し、正しく書けるようにしておくと、中学での学習がスムーズになります。
要約の練習や、文章の中から答えを見つける問題に取り組んでおくことで、定期テストにも対応しやすくなります。
英語
中学から本格的な英語の授業が始まるため、アルファベットの読み書きや基本的な単語の意味や文法を復習しておくことが大切です。
また、簡単なあいさつや自己紹介ができるように練習しておくと、授業にスムーズに対応できます。数字の読み方や、曜日・月の名前などの基本的な単語を覚えておくことも役立ちます。
2. 中学の予習をしておこう
中学の授業は小学校と比べて進みが速くなり、内容も難しくなります。少しでも予習をしておくことで、授業についていきやすくなり、良いスタートダッシュができます。
特に、最初に習う内容を事前に確認しておくと、スムーズに学習を進めることができます。
数学
中学の数学では、正負の数や文字式が最初に登場します。小学校では扱わなかった負の数の概念をしっかり理解しておくと、計算ミスを防ぐことができます。
また、文字式を使った計算がスムーズにできるように、簡単な問題に取り組んでおくと良いでしょう。
英語
中学の英語では、be動詞(am, is, are)や一般動詞(like, have, play など)を使った文章が基本となります。これらの文法を少し予習し、簡単な英文を作れるようにしておくと、授業の理解が深まります。
また、教科書の初めに登場する簡単な英単語を少しでも覚えておくと良いでしょう。
国語
中学の国語では、説明文や論説文の読解がより高度になります。文章の要点をつかむ練習や、筆者の主張を読み取る練習をしておくと、スムーズに授業についていくことができます。
また、中学からは古文の学習も始まります。竹取物語や百人一首など、簡単で身近な古典に触れておくと良いでしょう。
理科
中学の理科では、物理・化学・生物・地学の4分野を学びます。最初に学ぶのは「身のまわりの物質」や「植物の成長」など、小学校の理科の延長となる内容が多いため、基本的な知識を復習しておくとスムーズに授業に入れます。
社会
中学の社会では、地理・歴史・公民の3分野(公民は通常中3で習う)を学びます。
小学校で習った日本地理や日本の歴史の流れを軽く復習しておくと、学習の土台を作ることができます。特に、歴史の年代や出来事の流れを覚えておくと、中学の歴史の授業が理解しやすくなります。
3. 自宅学習の習慣を作る
中学では宿題の量が増え、定期テストに向けた勉強も必要になります。日頃から自宅で学習する習慣をつけておくことが必要となります。
自宅学習の習慣を身につけるためには、毎日決まった時間に机に向かうことが大切です。短時間でも良いので、毎日勉強する習慣をつけていきましょう。
また、学習計画を立てることで、何を勉強すべきかが明確になります。テスト前に焦らないように、日々の学習を計画的に進めることが大切です。
例えば、今日は数学の計算問題を解く、明日は英単語を10個覚えるなど、小さな目標を立てると続けやすくなります。
また、学習した内容を振り返る習慣をつけることで、知識が定着しやすくなります。ノートにポイントをまとめたり、間違えた問題を見直したりすることで、効果的に復習ができます。
自宅学習をする際は、勉強する環境を整えることも重要です。スマホやゲームなどの誘惑を避けるために、勉強中はスマホを別の部屋に置くなどの工夫をすると良いでしょう。
自宅学習の習慣が身についていれば、中学に入ってからの学習もスムーズに進めることができます。無理のない範囲で毎日コツコツと学習を積み重ねていくことが大切です。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」

中学入学準備【持ち物の準備】
中学入学に向けて、必要な持ち物をしっかり準備しておくことが大切です。小学校とは異なり、制服や指定の持ち物が増えるため、早めに確認し、揃えておくことでスムーズに新生活を迎えることができます。
最後に、制服や体操服、文房具、その他の必需品について詳しく解説します。
1. 制服や体操服
中学では、多くの学校で制服や体操服が指定されています。入学説明会や案内資料を確認し、サイズや購入時期を決めておきましょう。
制服は、成長期に備えて少し余裕のあるサイズを選ぶと良いです。ただし、大きすぎると着づらくなるため、試着をして適切なサイズを選びましょう。
冬服と夏服がある場合は、どのタイミングで着用するかも確認しておくと安心です。制服に合わせた靴や靴下の指定がある場合もあるため、購入前に学校のルールを確認しておきましょう。
体操服も指定のものがある場合が多く、学校によってはジャージや運動靴の種類が決まっていることもあります。
体操服は週に何度も使用するため、洗い替えとして複数枚準備しておくと安心です。
運動靴についても、体育の授業だけでなく部活動で使用することを考え、履きやすいものを選びましょう。
2. 文房具
中学では、小学校よりも授業の内容が高度になり、使用する文房具の種類も増えます。学校指定のものがある場合は、それに従って準備することが大切です。
ノートは科目ごとに使用するため、ある程度の冊数を用意しておく必要があります。
使用するノートは、罫線の幅やサイズが指定されていることもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。また、鉛筆やシャープペンシルは、書きやすいものを選び、消しゴムも使いやすいものを用意しておきましょう。赤ペンや青ペン、蛍光マーカーなども、ノートをまとめる際に便利です。
数学では定規やコンパス、分度器が必要になるため、授業が始まる前に準備しておきましょう。
筆箱はシンプルで使いやすいものを選び、必要な文房具がすぐに取り出せるよう整理しておくと、授業中の効率も上がります。
3. その他(弁当箱、水筒、上履きなど)
学校によっては、給食ではなくお弁当が必要な場合があります。
弁当箱は持ち運びしやすいサイズのものを選び、保温機能があるものが便利です。お弁当を持っていく場合は、保冷バッグやフォーク・スプーンなどのセットも準備しておきましょう。
水筒は、部活動や体育の授業の際にも活躍します。暑い時期には、保冷機能のある水筒が便利です。学校のルールによって、水筒の種類や飲み物の種類が決まっている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
上履きも指定のものがある場合が多く、学校のルールに従って準備しましょう。
サイズが合っていないと歩きにくくなるため、履き心地を確認してから購入することが大切です。靴袋が必要な場合は、通気性の良いものを選びましょう。
その他、学校によっては雨具や折りたたみ傘、体操服を入れるバッグなどが必要になることもあります。持ち物のルールは学校ごとに異なるため、入学説明会や学校からの案内をしっかり確認し、必要なものを揃えておきましょう。

まとめ
中学入学は大きな環境の変化となるため、事前の準備が大切です。
入学手続きは進学先によって異なるため、入学説明会に必ず参加して、確認を忘れずにしましょう。また、持ち物の準備も早めに進め、制服や文房具のほか、必要なものをしっかり揃えておきましょう。
計画的な準備を整え、中学生活のスタートを安心して迎えましょう!
家庭教師のマスターでは、新中学1年生の学習サポートを行っています。ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























